INDEX
|
�V�D�n�c�Ì��z ���t�̂ƒʐ� ���t�W����ɁA�z�c���̗L���ȉ̂�����B �n�c�ÂɑD�悹�ނƌ��҂ĂΒ������ȂЂʍ��͞Ԃ��o�ł����̉̂́A661�N�̕S�ϋ~���푈�̎��A�Ė��V�c�̑D����g�Ái�Ȃɂ�j����}���Ɍ������r���ɂ����ĉr�܂ꂽ�̂ł���B�n�c�Ái�ɂ����j�͍��̏��R�̓��㉷��t�߂̒Ái�D����j�ł���A������D�o�����V�c�̑D�͈�H�A�}���̛P�m��Ái�Ȃ̂����j�Ɍ����������̂Ƃ���Ă��āA���ꂪ�A���݂̒ʐ��ɂȂ��Ă���B �w���{���I�x�͂��̊Ԃ̌o�܂��ȉ��̂悤�ɋL���Ă���B ���N�t�������э�p�ЁB��D�����B�n�A���C�H�B�b�C�B��D�����唌�C�B����c�P�c���Y�����B���������H�唌�c���B�M���B��D�����ɗ\�n�c�ÐΓ��s�{�B�q�n�c�ÁB���]���k�ɓ��B�r�ʐ��Ƃ������̂́A�����̐l���S�̒��ł��ꂪ�������₷���ӂ��킵���ƔF�߂����̂ł���A���̈Ӗ��ł͂ЂƂ̐^���ł����āA�����ے肷����̂ł͂Ȃ��B�������A�ʐ��Ƃ����ǂ��A���j�̎����ƈقȂ�ꍇ�͂悭���邱�Ƃł���B ��������661�N�A�S�ϋ~���R�����シ�邽�߁A�Ė��V�c����g�Â��o�q�����Ɍ����������Ƃ͊m���ł��낤�B�������A����ȊO�̒n���I�Ȏ����ɂ��ẮA����𗠕t����؋��Ȃǂ͂قƂ�Ǒ��݂��Ȃ��̂ł���B �ʐ��̖��_ �܂��A�u�Ė��I�v��ǂ�ł݂�ƁA�O�N�ɒ}���Ɍ�K����Ƃ͏����Ă��邪�A�V�N�P���ɒ}���Ɍ��������Ƃ͂ǂ��ɂ������Ă��Ȃ��B�u�����������v�Ə����Ă��邾���ł���A"�S�ϋ~���푈"�̐��������A���̂܂ܒ}���Ɏ��������̂ƍŏ�����v������ł���ӂ�������B ���ɉ��R������l�����֓n�����̂͊ԈႢ�Ȃ����A�ɗ\�ɔ��܂����̂��A���̋{�i����j�Ƃ͏����Ă��Ȃ��B�n�c�Â̐Γ��s�{�i�����̂���݂�j�ƋL���Ă���̂ł���B����Ȃ瘮���V�c�̋L�����瓒�̋{�Ə����̂��ӂ����낤�B����́A�́A�����V�c�ƍc�@�����̋{�Ɍ�K�����Ƃ����L���������ɂȂ��Ă��āA�Γ��s�{���ƌ�F���Ă���̂�������Ȃ��B ����ɁA�u�P�m��Áv�̒n������A�n�c�Â����D����H�A�}���֑D������������̂Ƃ̒Z���I�ȉ��߂݁A�s������������Ȃ����A���邢�͍s���Ȃ�������������Ȃ����ƂȂǂ́A�܂�ŋ^���Ă��Ȃ��Ƃ������悤�B �n�c�Â̌��n�Ƃ��ẮA�O�Ð��A�x�]���A�������A������A����ɂ͋�B���Ȃǂ܂ł��邻���ŁA�������X�Ƃ������Ƃ���ł���B�������A�ɗ\�Ə����Ă���̂�����A������Ȃ�ł���B���͂Ȃ��ł��낤�B �����A�w�ɘ������y�L�x�핶�ɁA�V�c�炪�ɗ\�̓��̋{�Ɍ�K�������Ƃ��T�x����A���̍Ō�ɐĖ��V�c�ƒ���Z�c�q�A��C�l�c�q�̖������邱�Ƃ́A�n�c�Ó�����Ӑ��ɂ͈ꉞ�A�L���ł��낤�B�ʐ��ɂ��Ă͈ꉞ�A���d�������B �������A�����͐����ɏZ��ł���̂ŁA������̎��_���炱����l���Ă݂����̂ł���B �����ɂ�����n�c�Ó`�� �悸�u�n�c�Áv�Ɋւ��āw�������x�̋L������Љ�Ă݂����B �w�������x�͓V�ۂU�N�i1835�N�j�����ˎ叼�����w�i��肳�Ɓj�̖��ɂ��A�˂̎�w�ғ���g���Y�a���i�Ђ̂��낤�ɂ��Ă�j�����S�ƂȂ��q���ꂽ�����˂Ɋւ���啔�̋��y���ł���B����a����́A�˗̓��̏����⎛�ЂȂǂɒ�o�������l�X�ȕ�����֘A���鑽���̕��������A�ØV��n��������̓`�������A�̓��̋��X�Ɏ���܂Ŏ��n�ɑ����^��Ŏ��������̖ڂŊm���߁A�V�N�̍Ό��������Ă���������������B���̓��e�͑���ɂ킽�鎖�ۂ�ԗ����Ȃ�����A�ᔻ���_���Ȃĕ邱�ƂȂ����f������A�����̏��q��D�悳���邱�ƂŌ㐢�̌����Ɏ�����悤�ɕҎ[����Ă���B���́w�������x���Ȃ���A�V���̐w�ŊۏĂ��ɂ��ꂽ�����̗��j�͂قƂ�ǐ^���ÈłƂ�������قǂ̂��̂ŁA���y�j�����̋M�d�Ȋ�b�����Ƃ���Ă���̂ł���B ���́u���m�����i���イ�ނ�j�v�̍��ɁA�ȉ��̋L����������B �����ɁA�Γ������̎Ђ���A���Y�����A
�����̊C�݂͌��݁A�����͖��ߗ��Ă��A�V�c�ɂȂ�A�ՊC�H�ƒn�тɕς���Ă���B�������A�ȑO�͉���̊C�ŁA�����ł͊C�ۂ�L�ނ��悭�̂ꂽ�̂ł���B������Âɂ́A�C�ݐ��������Ɠ����ɓ��荞��ł����B�������A����]�̂悤�ɌE��ł���̂ŁA�M�͒����₷�������Ǝv���B���̒n���n�c�Âł����Ă�����s�v�c�͂Ȃ��̂ł���B ���m�s�{�Ƒ��R�_�� ���Ɂu�P�m��Â̔��m�s�{�i���킹�̂���݂�j�v�Ɋւ��Ăł��邪�A�w�������x�ɂ́A���������˗̓��̓y���̑��R�_�Ёi�ނ��܂���j�̍��Ɏ��̋L�q������B �c�Ђ̌Â����A����ςċ����Ɋ��w����A �c�����c �����ɁA�A�T�\�ؒ��g�̐�A����ƌāA �V�q�V�c �y���̒��q���A���n�ɍs�K����āA�V�_�n�L ���Ղ��T���Aᷟ����肵���Ɖ]�A�����A���� �ɂ�⑂鎖�Ȃ��A��c�ɗ��ĜA�v���Ȃ��A�v �c�c�����c�c���R�_�Ђ͓y�����Í��i�ǂ����傤�ˁj�ɂ���B�̂��炱�̎Вn��Øe�̐X�ƌ������̂ł��낤�B���͓��������A�����͕����ʂ�C�ݐ��ł��������Ƃ������Ă���B ��D���҂��� ���ꂩ��A�Ė��V�c���}���֍s�����̂��s���Ȃ������̂��A���ꂪ��Ԃ̖�肾���A���̌��ƂȂ�̂��A �O�����\��M�\�B��D�Ҏ����P��ÁB�������s�{�B�V�c�����A���H�����́A�u��D�ҁv�Ƃ������̈Ӗ����ǂ���邩�ɂ���B����ɂ́A��ʂ�̉��߂��\�ł����āA�@�D��{���̍q�H�ɋA���A�A�D�̍q�H���t�ɖ߂��A�̗������l������B�@�̏ꍇ�́A�D���ꂩ�牫���̖{���̍q�H�ɓ����ĕ��⒪�ɏ�邱�Ƃł���A���̂܂ܒ}���Ɍ����������̂Ǝ���B�A�̏ꍇ�́A��Ƃ��ẮA�M�c���̐Γ��s�{����A�ʉ߂��Ă��������֑D��߂������ƂɂȂ�A�n�c�Â����R�ɂ��Ă������ɂ��Ă��A�D�𓌂�����A�F���S�̒Øe�̓m�Ɏ���͕̂s�v�c�łȂ��B��Ƃ��ẮA�\���͏��Ȃ����A�ʂ̑D���}������}���ɗ��āA�V�c���悹�Ĉ����Ԃ����Ƃ̉��߂��\�ł͂��낤�B �@�A�̂ǂ�����ꉞ�A�[���ł��邪�A�������A�����Ƃ��Ă͌��݂̂Ƃ���A�ǂ���̐����̂��Ă��Ȃ��B���̋L���́u��D�ҁv�́A�}������Øe�̓m�ɐĖ��V�c�𑗂�A�����Ӗ��ɍl���Ă��邩��ł���B�ʐ��ł͂R���́u��D�ҁv�̋L�q���A�Γ��̒���ɑ������̂Ɠlj����Ă��邽�߁A�Q�������܂�Γ��s�{�ɐ����������ƁA���̂܂ܒ}���Ɍ��������Ƃ����̂����A���ۂ͂����łȂ��B�n�c�Â̋L���ƁA���̂R���̋L���̊Ԃɂ͑傫�ȃu�����N������B���̓�̋L���͈�U��Ă���̂ł���A���̂Q�������܂�̊ԂɐĖ��V�c�͒}���Ɏ���A���R������R�����ە����Ă���A�ɗ\�ɋA���Ă����̂ł͂Ȃ����낤���B
�Ė��V�c�̖��� ���̂Q�������܂��ł̓����̂��߂Ƃ��A�������W�������邽�߂̊��Ԃł���Ƃ̉��߂��\�����A�S�ϋy�ю����̑��S���������}�̎��ɂ̂�т蓹��̓��ɒ������ł��Ȃ����낤�B�܂��O�N�A�V�������̂��߂ɑD�点�A���ɕ�����g�{�ɏW�߂��Ə����Ă͂��邪�A�S�ς⍂��킪�U�߂��낤�����Ƃ͑O�N����̎��m�̎����ł���B�ً}�̎x����v������Ă���̂ł���A���R��R���A�D�═��Ȃǂ̑唼�͂��łɒ}���ɑ��荞��ŁA�R�c�����W�����������̂Ǝv��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�㑱�̑D�c���A���Ȃ�̏����E�ߎ��͔����Ă����Ƃ��l�����邪�A�Ė��V�c�̖����͎���}���̑O���ɏo�����ď��R����ە����A����o�����Ƃł���A�Q�����L�]���ɗ\�̓����ꏊ�ő�R�����W���Ă���]�T�Ȃǂ͂Ȃ����낤�B�܂����̂悤�ȏꏊ���Ȃ��A�^�~�̖�Ԃɉ����Ƃ��Ă��A���R����Ȃǂ̊C�l�ő�l���������ԁA�k���Ȃ���J�I�𗽂��邾�낤���B�^��ł���B ���������ĐΓ��s�{�ɂ́A����قǒ����������Ȃ��������̂Ǝv����B�Q�������܂�̓���������A�V�c�͒}���֏o�����ď��������サ�A���ꂩ��ɗ\�ɋA���Ă��邱�Ƃ͏\���A�\�Ȃ͂��ł���B���̍s���悪�ɗ\���F���S�i���܂���j�̒Øe�̓m�i���݂̑��R�_�Ёj�������̂��낤�B�w�������x�ɂ����̂悤�ȋL�����o�Ă���B ���{�I�E�V���I�ɁA�����O���i���F�V�N�R���̌�肩�j�A �}�������t�A�āA���P��Ãj���Ƃ���A�ߓ� �{�I�ɁA����������l�w�āA���̈ɘ����F���S�� �Ɖ]�Ƃ�����ЙB�Ɍ��w����A�w���{���I�x�ɂ́u�}�����v�Ƃ̋L�q�͂Ȃ����A�w�������x�ɂ́A�Г`�Ƃ��Ă��낤���A���������Ă���B �܂��w���{���I�x�ɂ͂�������������Ă��Ȃ����A���̒}���ւ̉����̓r���ɂ����āA�V�c�̔���������߁A�������x�A����̓��̋{�ɑ؍݂������Ƃ͍l�����邱�Ƃł���B���������āA�Ė��V�c�������ɑ؍݂����Ƃ̓`�����������R�n���ɑ��݂���̂ł���A����́A���Ԃ�A�H�ł͂Ȃ��A�����̐Γ��s�{����}���������r���ł̒Z���Ԃ̑؍݂ł���A�w�ɘ������y�L�x�핶���T�ԖڂɋL���Ă���̂��A�����炭���̎��̂��Ƃł��낤�B �������A�Ė��V�c��c�q�i�݂��j�炪����ɗ������������Ƃ����āA���オ�Γ��s�{�Ƃ����킯�ł͂Ȃ��B�������A�n�c�Âł��Ȃ��̂ł���B �Øe�̓m�ɋA�������R �}������D���҂����Ė��V�c�̈�s�́A�F���S�̒Øe�̓m�ɒ������B���������̍s�{�i�w�������x�Ɉɘa���̋{�Ƃ���j�ƌĂ�A�܂����Ái�Ȃ��j�̋{�Ƃ��Ă��A���݂̑��R�_�Ђ̎Вn�ł������B
�Ȃ��}������A�����̂��B���X�}���Ɉڂ�\��܂ł͂Ȃ������̂�������Ȃ����A�����̋ٔ���������67�Ƃ��v���鏗��̑̒����}���őς���ꂽ���ǂ����B�틵�ɂ���ẮA�S�ϋ~���ǂ��납�A���̑D�c�ɒ}���܂ōU�ߍ��܂�鋰�ꂷ�炠�����B��̐Ė��V�c���C����������Z�c�q���A�ƒ}���̒��Ԃ�����ɂȂ�ɗ\�̉F���S�ɑނ��悤�V�c�ɏ�\�������Ƃ��l�����悤�B ���R�_�Ђ̓m�͒Øe�ɂ���A�����炭����̒����C�ݐ��������Ă����̂ŁA���̂�����ÂƌĂ̂��낤�B���Â̘e�ɂ������̂ŁA�Øe�̋{�Â̋{�Ƃ��̂����Ǝv����B�P��Ái�Ȃ̂����j�̖��̂́A�V�c�̋{���ڂ������Ƃ���A�����̛P��Â̖��̂����̂܂܈ړ����������̂�������Ȃ��B�����A�V���l�A�y���̂�����͒n�`���p�����Ă���A�����p�ɂ��������Ă���悤�ł���B �ł́A�Ȃ��y���̒Øe�̋{���s�{�ɑI�ꂽ�̂��낤���B�w�������x�͎��̂悤�ɑ����Ă���B �������ɍc�q�˂Ɖ]����A�V�q�V�c��[�J]�̎��A �c�q���I�V�ʂЂ��邠��āA���˕�̚Ж�Ɖ]�A �����{�Ɖ]�n����A�����V�q�̑��q�̋{���̐Ֆ�Ɖ]�A ������������b���s���m���ǂ��A���R�ЙB�̖����L���V�q�V�c�i����Z�c�q�j�����̒n�ɑ؍݂����̂��ǂ̎����������̂�������Ȃ����A���ꂪ�Ė��V�c�̌�K���ȑO�ł���A���łɂ��̉F���S�y���̒n�Ƃ͊W���[�������̂ł��낤�B�������A����͐Ė��V�c�������̏o�����ł�������������Ȃ��B������ɂ��Ă��A���̒˂ɊY������悤�ȓV�q�V�c�̍c�q�͍��̂Ƃ��댩������Ȃ��悤�ł���B�V�q�V�c�̍c�q�̈�l�ɂW�Ś�܂����Ƃ���錚�c�q�Ƃ����c�q�����邪�A�w���{���I�x�ł͐Ė��V�c�S�N���I���i��������j�ł���A��a�Ɏ��߂�ꂽ�ƋL����Ă���B�������A�I���̏ꏊ�܂ł͏�����Ă��Ȃ��B �܂��A���݂��Гa�̑O�ɂ����ˁi��������Â��j�ƌ������̂�����B�O�q�́w�������x�ɁA �БO�ɛ��˂Ɖ]����A���܊Ԉʂɏ������z���A ����n�A���̓V�c�A�Վ��I��āA�_��߂���Ֆ�Ɖ]�A ����Ƃ̎��A�x���߂���ɁA���ق���ɕ|��āA�����~�ʂƉ]�A�������X�o�����ƂāA���ɚ����邪�@�L���̐����{�Ђ��U�ށA�w�������x�ɂ͂��̏o�y���̐}���ڂ��Ă��邪�A�`���ɂ��ƁA���̂����˂͏�L�̂ق��ɁA���M�ȕ��̗˂ł���Ƃ��`�����Ă��邻�����B�����ɓV�c�i�V�q�V�c�j������s�����Վ��Ƃ́A�c�q���I���Ɋւ�����̂ł������̂��낤���B����Ƃ��Ė��V�c����̌�A����Z�c�q�����q�̋{������̍s�{�ɋA�����Ƃ��̂��̂������̂��낤���B�����������u�Ė��I�v�̔��̋{�ł���̂Ȃ�A�a�v�����ߎ��̕�A���邢�͐Ė��V�c�̉��˂Ȃǂł������\�����ے�͂ł��Ȃ����낤�B �Г`�ɂ��ƁA�u���_�V�c�̌��`�������̒n�ɉh���A�����čF���V�c�̌��A�������a�����i���ׂ̂��ǂ̂����܁j����̗��i�Í��̗��j�ɔh�����ꍻ���̍̏W�ɓ������B�v�Ƃ̂��Ƃł���B�̓��V�c�V���_��Q�N�R���R�����ɂ��A�����łȂ��鍻�i���コ�j�ł��邪�A�����Ɋ֘A����L�����f�ڂ���Ă���̂ŁA���̈���������`���Ƃ̐l������莝���������������̂�������Ȃ��B�V�q�V�c�̛l�i�݂߁j�̈�l�ɋk���i�����Ȃ̂���߁j������A���̕������������𖼏���Ă���B ���q�̋{ �Ė��V�c�͂��̔��̍s�{�Ɏb���������ƁA�T���ɒ��q�k�L��{�Ɂi��������̂����Ȃ̂Ђ�ɂ�݂̂�j�Ɉڂ������Ƃ��w���{���I�x�ɏ�����Ă���B �܌�������ᡉK�B�V�c�J�������q�k�L��{�B�����B�̋ҏ����q�ЖA���썟�{�V�́B�_�|��a�B�����{���S�B�R����ɐl�y���ߎ��a���ҏO�B�ʐ��ł͂��̒��q�̋{���A���������q�����邢�͒��q�s�Ȃǂ̐_�Вn�Ƃ��Ă��邪�A�������A�F�����ɂ��Ɠy���̒��q�_�ЂɂȂ��Ă���B���q�̋{�ɔ�肳���ꏊ���}���ɂ���̂�������Ȃ����A�Ė��V�c���F���S�ɋA��A���̒n�̔��̍s�{���璩�q�k�L��{�Ɉڂ��ĕ��䂵���̂Ȃ�A���̓����Z��ł����ꏊ�������l�����̒��q�̋{�ł���\���͎�m�ł��悤�B
�Ė��V�c�̕��� �����āw���{���I�x�͎��̂悤�ɋL���B �H�����b�ߍ��B�V�c�������q�{�B�y�����q�_�Ђ̗��ɂ��O�֎R�Ɏ����_�ޔ��R������A�ԋS�R�ƌ����������B�S���`���Ă����Ƃ����`���ƊW������̂��낤�B�R�̏�Ɋ}�_���������ĉ����Ƃ����L�q�́A�Ė��V�c�̎��ƁA�S�ϋ~���푈�̍s���ɑ���s����������A�����̐l�X�̊ԂɍL�����Ă����s���Ɠ��h�̑傫�������̂ł͂Ȃ����낤���B ���q�{�͒}�����y����
�����ŁA�l���̂��̂悤�ȏꏊ�ɂ��āA�~���푈�̏����⍷�z���\�Ȃ̂��Ƃ����v��������B�������A�N����l����A��x�x�Ȃǂ͍c�q�⏫�R��ɔC���Ă����悩�����̂�������Ȃ��B�ق��ɂ�67�i���j�ŋߎ��������A��āA�ǂ�ȕ��@�œy���܂ňړ������̂��낤���B�����l���R�����z�����̂��B�C�݉����̑D���ł͂����ւ�ȑ���ɂȂ邽�߁A�^��������Ȃ��킯�ł͂Ȃ��B�}���Ɠy���Ƃǂ��炪�������̂��B�m�F����p�Ȃǂ���̂��낤���B �w�V�Í��W�x�Ɂu���q��̊ۓa�ɂ킪����Ζ��̂�����s����N���q���v�Ƃ����A�V�q�V�c�̉r�݂Ƃ����̂�����B ����Ɋւ��āA�w���Q���ޏ]�x�Ɏ��̈ꕶ���������B ���Q���ޏ] 19��(�nj���) ���یȈ� �ҏW���̒��҂̈Ăł͒}�������̗p���Ă��Ȃ��B�}���ɂ͂܂������o�����Ă��Ȃ��Ƃ����̂ł���B���R�_�Ђ̓`�����u��D�ҁv�̋L�q�������Ƃ��āA���݂͂��̐��炵���B �Ȃ�ق��A�n�c�Âŗv�l�̑̒��������������ߒ}���s����f�O���A��҂��Ă���F���S�ɑD���҂����Ƃ����ݒ�Ȃ�A���̂悤�ȃP�[�X���F�ߓ��邾�낤�B�����Ƃ��A���̏ꍇ�͉F���S�����A����̓��̋{�œ����ł������ق����悩�����̂�������Ȃ����B�����A�u�䏊�Ԃ��v�Ƃ͉��ƂȂ��C�ɂ����錾�t���B �������w���{���I�x�ɂ́A�Ė��V�c�͑O�N�A�}���ɏo�����ċ~���̏��𑗂낤�Ǝv���āi�u�v�K�}�������~�R�v�j�ƋL���Ă��邱�ƁA���̂܂܂ł͏n�c�Âł̂Q�����]�̑؍݊��Ԃ͒������邱�ƁA�}���Ǝl���̗����ɓ`���n�����邱�ƂȂǂ��l������ƁA��x�͒}����K�ꂽ�̂ł͂Ȃ����Ƃ��������͂���B�����A���R�_�Ђ̋�̓I�ȓ`����n�������邩����A���̂܂ܒ}���ɑ؍݂��Ē}���ŕ��䂵���Ƃ́A�ǂ����Ă��v���Ȃ��悤�ł���B ���݂Ɉɗ\�̍����ɂ����q�̒n��������A�֘A���͕�����Ȃ����A�Ė��V�c�̓`�������݂���Ƃ̂��Ƃł���B�Γ��s�{���������A���̋{�Ɍ������r���ŁA����������̂��낤���B�������A�R�����������̘b������A���q�̑����ɉ����Ė̊ۓa�̓`��������̂ł���A�Ė��V�c�A�V�q�V�c�A�������̎҂��y���Ȃǂ̒��q�{����Ĉړ��������Ƃ��l������B�Ñ�ɂ����āA�l�ƂƂ��ɒn�����������Ƃ͂悭���邱�Ƃł���B�i�㒍�j �w�������x�͑��R�_�Ђ̍Ր_�Ƃ��đ喤�M��������L���Ă��邪�A���݂̎�Ր_�͓V�Ƒ�_�A����ɐĖ��V�c�ƓV�q�V�c��z���Ă���悤���B�V�Ƒ�_�͕����Õʖ��i�������ɂ���킯�݂̂��Ɓj����ɑ]�T�_�Ђ���݂Ǝv���邪�A�Ė���V�q���V�c�̕�ՔN�͕�����Ȃ��B���̘^�ɂ́u�Ė��V�c�͓V���V�c���P�W�N�W���̕�ՂƉ]���v�ƋL����Ă���Ƃ̂��ƁB�Г`�ł����P����ɂȂ��Ă���炵���B���ꂪ�������Ȃ�A�V�q�V�c���������ł��낤�B�������A�����̍Ր_���w�������x�ɋL����Ă��Ȃ��̂������B ���A���R�_�Ђɂ�70�]�̖̂ؑ�������A�Ė��V�c�ߎ��̐����ƌ����A���̈�͓̂V�c�̑��Ƃ������Ă���Ƃ̂��Ƃł���B ���łȂ���A����17�N�́u�Í����n���v�ɂ��ƁA���R�_�Ђɂ͎ЋL�̎ʂ��Ƃ������̂�����A�V���T�N�R���̉z�q�^�̋L�q�ɂ��Ɠ`���Ă���B�z�q���͓������̒n���̑�̂ł������Ƃ���邪�A�w���{���I�x�ɐĖ��V�c�̗˂����s����ˁi�����̂����̂����݂̂������j�Ƃ��Ă��邱�ƂƉ����֘A������̂��낤���B �b�͛P�̑�ÁA���̍s�{ �A���q�̋{�̂ق��ւƈ��Ă��܂������A���R�_�Ђ͓��������˗̓��ł�����A�����͏n�c�Â̌��ؒn�ƊW������̂ōl���Ă݂��܂łł���B
���āA�Γ������{���������Ƃ������m���i���イ�j�̋߂��A�����s�B�V���i���̂����j�ɂ͌��݂����V�J����i��̂��ɂ���j�Ƃ���������B�P�������̏��K�͂ȓ��A�艷���h���{�݂�����A���悢���߁A���������l�C������B ����{�݂̖k���͕��삾���A�쑤�͎R���}�Ζʂɗ������R��ɂȂ��Ă���A�����͌Ñ�̒f�w�ՂƎv���A����͒����\�����̐^��ł���B����𐼂։����ƍ��ꔼ��������łقړ��㉷��̓���ɘA�Ȃ�B�����āA����ɉ�������ƈɗ\���n���ĕʕ{����Ɏ���̂ł���B�w�ɘ������y�L�x�핶�ɁA��ȋM�������F������h�������悤�Ƃ��āA�ʕ{�̓���n�����瓹��Ɉ������Ƃ̘b�����邪�A����́A���̒����\�����̂��Ƃ��w���Ă���̂ł͂Ȃ����낤���B���̐���ɏB�V���̓��V�J������B�������Ă���A�w�������x�ɂ͓��₪�������Ə�����Ă���B�Γ��Ɗւ�肪���邩�ǂ���������Ȃ����A���̒n�ɓ�������z�������Ƃ��Ă��s�v�c�ł͂Ȃ��n���I�����ł���B�u�Γ��s�{�v�Ƃ́A�����炭�A�s�{�̋߂��ɗN���o���z�������Ƃ��납�疼�Â���ꂽ���̂ł���A�����V�c�������ʼn���ɓ������Ƃ����悤�Șb�ł͂Ȃ����낤�B
��o���t�w�ݗt�W���߁x�ɁA �u�ɘ������y�L�j�n�㉪�{�V�c��̞H ���k�������g�V������k�]�X�i�ɘ������y�L�ɂ́A��̉��{�̓V�c�̌�̂ɉ]�킭�A�݂����ɔ��ĂČ���A�]�X�j�v�Ƃ��邱�Ƃ���A�u�ɂ����v�́u�݂����v�̂��ƂŁA�u�Ɂv�Ɓu�݁v�͑��ʂ����t�ł���Ƃ��Ă���B�܂��u�ɂ��v���u�a�v�Ƃ��āA�u�ɂ����v�͋F�������Đ_����a�炰�A�n�C�̕������F��Ӗ��ɉ��߂��Ă���悤���B �������A����ł͏n�c�Â̏ꏊ���܂�����������Ȃ��B�����ŕʂ̉��߂����Ă݂����B �u�ɂ����v�́u�݂����v��\���Ȃ�A�u���k �i�w���{���I�x�ɏn�c�Â͎��k�ɓ��Ɖ]�A�Ƃ���j�v�Ɓu���k�v�͓����Ӗ��ɂȂ�B�u���v�́u�c�Áv�̈Ӗ��œ����ł���B�͂����āu���k�v�Ɓu���k�v�͓������낤���B�����炭�قȂ�̂ł͂Ȃ����Ǝv���B�܂��u���k�v���猾���ƁA����́u���v�̂��Ƃł͂Ȃ����ƍl����B���̃q���g���A����z�[���y�[�W���狳���Ă�������B����ɂ͈ȉ��̂悤�ɏ�����Ă���B ���́u�n�{�c�Áv�̍l�����̍����̈�ɁA�Ė�����̉̂�����B�ɗ\���y�L�ɂ��A�n�c�Ð����̍ۂ̐Ė�����̉̂Ɂu���k�i�݂��j���Ɂ`�v�Ƃ����̂��������Ƃ����B����̉̂͏��傪�c�邾���őS�Ă͕�����Ȃ�����A�u�݂��v�������Ӗ����錾�t���͕����łȂ��B�����u�݂��v�̌��Ƃ��Ắu��K�v�u�����v�u�O�v�u���v���̒n�����l�����Ă���B������ɂ��Ă����̂��Ƃ́u�݂��{�c�Áv�ł��������Ƃ̏؋��ɂȂ邾�낤�B�܂�A���́u���k�v�́A������������u���v�������̂ł͂Ȃ����B �Ȃ��Ȃ�A���̐����̒n�͐����V�c�̎���ɕ����Õʖ����c�Ђ��O�߂��Ɠ`������u�䑺�i�݂ނ�j�v�̒n�Ȃ̂ł���B�u���v�Ɓu��v�͌����܂ł��Ȃ����`�ł���B�_���ȏꏊ�ł́u�_�v�̎����g�p����B�w��㋌���{�I�x�ɂ͌i�s�V�c�̍c�q�̂ЂƂ�ɕ����c�ʖ��i�������ɂ��߂킯�݂̂��Ɓj�����āA�u�ɗ\���ʁE�Y���N�̑c�v�Ƃ��Ă���B�����c�ʖ��͕����Õʖ��̂��Ƃł��邪�A��ɕ����Õʖ���}�����ԌN�̑c�Ɏg�p���Ă��邩��A�����c�ʖ��ƕς��Ă��邾���ŁA�����́u�ʁv�݂͂ȁu�c�ʁv�ł���B�w���{���I�x�̂ق��ɂ́A�����Õʖ��͈ɗ\�䑺�ʂ̑c�Ə����Ă���B���݂ɓY���N�́u�Y�i���Ӂj�v�͐����s���z�i���イ�A�̂̎��~�S�j�̂��ƂƎv���A�w��㋌���{�I�x�ɂ��ƁA���҂Ƃ��ɁA���̒n�̕ʥ�N�͌��I�ɂ͕����c�ʖ��̎q���ł���B �]���āA�u���k�����v�Ƃ́u���c�Áv�̂��Ƃ������Ă���̂ł��낤�B�Ė��V�c�́u���k�����]�X�v�̉̂��r��ł��邪�A�u���c�Áv�ł́A���ЂƂ��̉̂̎����Ă��鍂�g���ɂ͌�����B�܂��A�P�Ȃ�n���Ƃ��������ł́A���̋�Ƃ̖������Ȃ��B�����ŁA�ߎ��̛ޏ��Ƃ��ċV���I�Ȋi�������̂�v�������z�c�����A�u�n�c�Áv�ɕς����̂ł͂Ȃ����Ƒz������B�u�n�v�����ꊴ�ɂ́A���i�Ƃ��j�Ȃǂ��n����Ƃ�������������B�����ɂ����������Č��⒪��҂��Ă���ƁA���悢�悻�̎��������Ƃ����͋�����ۂ�����B ���́u�n�c�Áv�ɂ́A�������̈Ӗ����l������悤���B���Ƃ��u�n�c�Áv���u�n�c�{�Áv�Ƃ����ꍇ�A�u�n�c�i�ɂ����j�v���u���キ�ł�v�Ɠǂ�Ŏ����������Ă݂�ƁA�u�Â�����k�삳�ꂽ�c�A�悭�k�삳�ꂽ�c�̂��Ƃ������v�Ƃ���B�܂��u�n�c�Áv���u�n�{�c�Áv�Ƃ����ꍇ�A�u�n�v�͉��₩�ł���A�u�c�Áv�͐��c�n�тɂ��鎩�R�̑D����i�l�Ӂj���w���Ǝv����B���̗p��Ƃ��ẮA�u�Ė��I�v�ɂ��A�]���ȉڈi���݂��j�Ƃ��āu�n�ڈv�̎��ĂĂ���B����Řp�����Ă������₩�Ȓ����l�ӂ́A�����̏M�̒┑�ɂ��K���Ă����ł��낤�B���́u�n�c�Ái�ɂ����j�v�́A�Ӗ������ꊴ��͋������t�Ƃ��āA�u���c�Áv�̑���ɖ`���ɍ̗p�����̂ł͂Ȃ����B������A�u�ɂ����v�Ɓu�݂����v�ł́A�ꏊ�������ł��Ӗ�����Ƃ��낪�قȂ�̂ł͂Ȃ����낤���B �n�c�Ñ��ɂ��� �ŋ߁A�l�b�g�Ɏ��̋L�����f�ڂ���Ă���̂��A���܂��ܖڂɕt�����B �����s�n�c�Ð��̒��ڏ؋��ł���j�����Љ��܂����B����́A�����s�̋k�V�{�_�Ђɓ`���ޗǎ��㖖���Ƃ����_���̓����ɏ����ꂽ�u�n�c�Ñ��k�v�̕����ł��B���̒n�悪�n�c�Ñ��ƌĂ�Ă�������ɏ����ꂽ�n���ƌ��Ȃ���܂��̂ŁA����͓�����j���Ƃ��Đ����s�n�c�Ð����ؖ�����ꋉ�j���ƌ��킴��܂���B����ɂ��A�Ė��I�̏n�c�Â������s�ł��������Ƃ͌���I�ƂȂ�܂����B����͊m���ɐV�����ł���B�u�ɂ����v���u�݂����v���l�ɒn���ł������Ƃ������ƂɂȂ�B�����u���k�v�Ɓu���k�v��������łȂ���A���̒��̏n�c�Ñ��ł��낤�B �������A�l���Ă݂�ƁA���̐_���̐���N�オ�������Ƃ��Ă��A�ޗǎ��㖖���Ə����Ă����āA�Ė��V�c�ȑO�ł͂Ȃ��̂ł���B������ƌ����Ă�100�N���Ⴄ�B���̂���ɂ́A���n���n�c�Â̓`���n�ł��邱�Ƃ��������Ă������߁A�n�c�Ñ��Ə̂����Ƃ������Ƃ����蓾�悤�B�P�ɏn�c�Â̒n�������ł����̂Ȃ�w�������x�̓�ؑ��i�Ȃ�̂��ނ�j�̉ӏ��ɂ��A�ۚ������N�Ɍ�����Ƃ��Ď��̋L��������B �������^�H�A�搥�A�S���k���L���ՉW�A���k�a�] �X�A�S���ҁA�_��S��A�a�����n�c�ÔV�g�ҏ��A�� ���L���W���A���މW�V�ÐՖ�A�������k���A���V ���m���E�Ð�E�㍻�V�ԁA���k���A����暖�����͐_��V�c�̋k�v�l�`���Ɋւ�����̂��Ǝv�����A�u�n�c�Ẩ��ҁi��������j�̏��v�Ə�����Ă��āA��̉W�����i�������j�Ƃ͏ꏊ���Ⴄ�悤������ǂ��A�n�c�Â̖����o�Ă���B �k�V�{�_�Ђ̑n�n�́A�R���ɂ��ƓV�q�V�c�ȑO�Ƃ���邪�A�B�V���̌��ݒn�Ɉڒz���ꂽ�͓̂V���N�ԁi1532�`1554�j�������ΐ쎁�ɂ��Ƃ̂��Ƃł���B����ȑO�̎Вn�͌��݂̈��m���V�J�̂ق��̋��Ղł������Ǝv�����A���̋��Ղ͐Γ������{�������Ȃ�k�̔��n�ɂ���A���Â͉���̊C���ł͂Ȃ��������Ƃ݂���B���������Ă��̋��Ђ��A���͂ǂ����R��̂ق�����㐢�Ɉړ]���ꂽ���̂ƍl�����ق����悢���낤�B �v�́A���̐_���̖����n�����ꂽ����ɁA�_�Ђ��ǂ��ɒ������Ă����̂��Ƃ������ɂȂ�B�k���ł���i�����͕X�����j�Ȃǂق��̑�������m���V�J�Ɉړ]������A���邢�͐V�{�Ƃ��Ċ��������̂Ȃ�A���̖n���́u�n�c�Ñ��v�̕�������_���͈ړ]��̍�ƍl�����悤�B�X�����i�Ђ݂ނ�j�͏n�c�Ñ��ł͂Ȃ�����ł���B �w�������x�̏B�V�����V�{���_�̍����u�����_�Ɖ]���̖ؑ���A���n�O�\�O����A�Ђɑ��āA���n��\�l���A�ʂɏ��K�����ē��V�A���_�[�O�\�O�n�A�����̐ΐ쎁�A�Ē������Ɖ]�A�v�Ƃ���A��L�̐_�����������̖ؑ����w���Ă���̂Ȃ�A�ΐ쎁���Ē��������̂ŁA�����ؑ���͂����̂��Ƃ��Ă��A�V���N�Ԃ�����̍�ł��낤�B���������Ėn�������̂Ƃ��ɋL�������̂ł͂Ȃ����B�ؑ����тɖn���̔N��̉Ȋw�I�����K�v���낤�B �n���́u�n�c�Ñ��k�v�̕�������l����ƁA���m���V�J�̂ق��̋k�Ђ�������w�����������邪�A�������ۚ������N�̋L�q���琄������ƁA��͂��Ƃ��A�B�V�������Z�����������A�Ð�i�ӂ邩��j�܂ł����A�k�̗��ł���A�n�c�Âł������悤�ȏ������ł���B���̋L���ɂ��̂܂]���A�n�c�ẤA���X�͕X�������肩��Ð�܂ł̍ג����C�ݐ��̑��̂̂悤�Ɏv���Ă���B�����āA���̂������т��k�̗��ƌ����āA���A�Ð�A���m���A�㍻�i�����j�Ԃ��k�̓��ƌĂ�ł���̂��A���̏؋��ł���Ƃ̂��ƁB���̕��͂���́A�����Ƃ������Ȃ��B�܂����c���̒n�����炢���Ă��A���c�͌㐢�ɕX�����y�яB�V�������Z���̈ꕔ���������̂̂悤�ł���A����Ȃǂɂ��A�����ɏo�����c�n�����琼�c���Ə̂����̂�������Ȃ��B�����琼�c���A�ꕔ�͏n�c�Â͈͓̔��ł͂��낤�B�������A���ۚ̕������N�̋L�q���̂����낵�Ă���̂�������Ȃ�����A�^�U�̂قǂ͕�����Ȃ��B�����A�n�c�ÂƋk�̗����������Ă���\���̂ق����傫�������B����ł��u�n�c�Áv�̖��̂����͔F�߂���B �u�n�c�Áv�Ƃ͊ȒP�Ɍ����A�u�g�Â��Ȑl���͂Ȃꂽ�l�Ӂv�̂��Ƃł��낤�B���ꂪ�A�Ė��V�c�̎���ɁA������n���ɂȂ��Ă������ǂ����ɂ��Ă͕�����Ȃ��B�������A�㐢�ɍ��ꂽ�ËL�ɂ��Ă��A�ؑ��ɂ��Ă��A�u�n�c�Áv�̖����L����Ă���̂ł���A���̒n���A�Â����疜�t�̂̏n�c�Âƍl�����Ă����L�͂ȏ؋��ɂ͂Ȃ邾�낤�B
������ɂ��Ă��A�n�c�Ẩ̂́A���̐����i���j�̌��݂̐��c������m��������̑D�������r���̂ł��낤�B�����ɂ͌�́u�Γ������{�v�ɓ�����Γ��s�{�̏ꏊ���������B�w���{���I�x�ɂ́u�n�c�Â̐Γ��s�{�v�Ƃ͂����菑���Ă���B�Γ������{���Ղ�������m���i���イ�j�̒n���ɂ��Ă͏]�����낢��Ȑ�������B���ɂ́A��Y�̑�c�P�c���i�������̂Ђ߂݂��j�����̒n�ő唌�c���i�������̂Ђ߂݂��j���A�o�Y���ꂽ�Ƃ̎ЋL�܂ň₳��Ă���炵���B�������A���̐��́w���{���I�x�̓��e�ƈقȂ�A�唌�c���̖����炢���Ă������I�łȂ��B����ɑ��鎩���̉��߂́A���ۂ͂Ƃ������ȒP�ł���B�唌�c���͑唌�̊C��Œa�������̂����A�Ė��V�c�͈��m���ɒ����Ă���A��c�P�c���̈��Y��m�����̂ł���B�Γ��������A���Y�����Ƃ���Ă���̂́A���̂��߂ł���B���m���̒n�������̌̂ł��낤�B �Ė��V�c�ƌ�� �V���S����F���S�ɂ����Ă̊C�݂́A���ꔼ���i�����Ȃ�͂�Ƃ��j����O��̊Ԃɂ����ĉ���Ŋ����p�����Ă���A�O������i�Ђ����Ȃ��j���L�����Ă���B�┑�n�Ƃ��Ă͓K���Ă������낤�B�܂��A�����Õʖ��̎q���̎��߂�y�n�ł���A�����Ȃ�x�������A�����邱�Ƃ��o�����ɈႢ�Ȃ��B���Ă̐_���c�@���V�������O��ɂQ�x����������`��������A���邢�͔��������̎��_�I���݂ł���_���c�@�����̒n�ŁA�~����ɔ����ēV�_�n�_���Ղ����̂��낤���B �w���t�W�x�n�c�Ẩ̂̌������߂ɂ͎��̂悤�ɏ�����Ă���B �E�́A�R�㉯�ǂ̑�v�̗��ډԗт������ɞH���A�c�c�����c�c��D�ɘ��̏n�c�Â̐Γ��̍s�{�ɔ��ĂB�V�c�A�̓����Ȃّ���镨���䗗�����c�����Ɋ����̏���N�����܂����B���̂��Ɉ���ĉ̉r���Ĉ��������܂Ђ��Ƃ��ւ�B���Ȃ͂����͓̉̂V�c�̌䐻�Ȃ�B�u���Ȃ͂����͓̉̂V�c�̌䐻�Ȃ�B�v�Ə����Ă��邪�A����́w���ډԗсx�ł͂Ȃ��A�w�ݗt�W�x�ҏq�҂̌����ł͂Ȃ��̂��낤���B�n�c�Ẩ̂̓��e�́A��������������悤�ȉ̉r�ł͂Ȃ��悤���B���̉̂����u�݂����ɔ��ĂČ���A�]�X�c�v�̂ق����A�܂�����ɋ߂��C������B�Ė��V�c�炪����̓��̋{�ɂ�����������̂ł���A�������ɁA20���N�O�ɘ����V�c�i����߂��Ă�̂��j�Ƌ��ɖK�ꂽ�Ƃ��̂��Ƃ��v���N�����Ċ����I�ɂȂ������Ƃ����������낤�B�������A����͉�������̓��̋{�ł̏o�����Ƃ͌���Ȃ��B�̓��ɓ���̓��̋{�Ɍ�K�����Ƃ��ɂ��A�C���痤�̕��i�߂Ȃ���A�D�Ő���������̊C�݂��ʂ��Ă������͂��ł���B���̂�����̌��o���̂��铇�e�Ȃǂ̌i�ς��A���������Ɗ����̏���ĂыN���������Ƃ����蓾�邾�낤�B���̒��ł��A�Ƃ��ɋk�̓����䗗�i�݂��Ȃ�j�����Ƃ��A�V�c�ɂ́A���Ƃ��犴�S�[���v����������ꂽ�̂ł͂Ȃ����Ƒz�������̂ł���B �k�̓��ɂ͂��̐́A�_���c�@���������V�_�n�_���Ղ����`�����������B�����āA�w�ɘ������y�L�x�핶�ɁA�_���c�@�̌�̂Ɠ`�����Ă��閜�t�̂�����B �k�̓��ɂ�����Ή͉��ݔ������D�Ђ��킪���������V�c�Ƃ̎v���o���ނ�������낤���A�����ł���Ė��V�c�͋k�̓������Đ̓��̐_���c�@���v���A�����̋��U�Əd�ˍ��킹�Ċ����̏������A���������̂ł͂Ȃ����Ƃ��v����B ���������A�����k�̓��Ɏᓒ�����i�킩�䂦�̂������݁j�̉r�݂Ƃ��������������B �V�̔g�ނ����ɖ������ւ��Ƃ��Ē�ɋk�̂�������͂�����������A���ۂɂ͐Ė��V�c�̐��̂������̂�������Ȃ��B������ᓒ��������삵�Ċ����������̂ł͂Ȃ����B�ᓒ�����ɂ͖��t�W�Ɏ��̈����B ���(������)�ɂ͒�(����)�������ČΕ�(�݂ȂƂ���)����������ޒÌ�(��)�̍�͂��������u�V�̔g�c�v�̉̂̂ق��́A���R�ł킩��₷���͂��邪�A�u��粁c�v�̉̂̂悤�Ȋi���̍����͌����Ȃ��B�k�̓��͕s�V�����̍��ʂ����铇�ł���A��Ԃ�̓��ł���B���̂悤�Ȏv�������߂āA67�̐Ė��V�c�͐̓��̐_���c�@���ÂсA����20���N�O�̉䂪�g���������̂ł͂Ȃ����낤���B ���Ƃ���A�o���̕�����Ȃ��ᓒ���������̎���̐l�ŁA�z�c����ƂƂ��ɐĖ��V�c�̋ߎ��̈�l�������̂�������Ȃ��B�z�c���͓������ł�����B�����𐳂Ƃ���A�ᓒ���͕��Ȃ̂ŁA�ᓒ�������ޏ��I�ȑ��݂������̂��낤���B �Ì�(��)�̍� �u���(������)�ɂ́c�v�̉̂ɂ��Ă��A�u�Ε�(�݂ȂƂ���)�v�������Ă��邱�Ƃ���A�ȑO�͔��i������̉̂��Ƒz�����Ă����B���ۂ��������������邪�A���ͤ���̂�����̉̂ƍl����悤�ɂȂ����B�K�������ƒf�ł͂Ȃ��B�ŋ߁A��g�̓��{�ÓT���w�S�W�̂��̉̂̓����Ɂu����A�܂����Q�Ƃ��v�̈ꕶ�������A�ӂ���Ǝv�����B�����l���Ă���͎̂��������ł͂Ȃ������̂ł��낤�B �n�c�Â̏ꏊ�Ƃ��֘A����̂ŁA����������̓I�ɏq�ׂ�A�����ł́A����͋k�̓��A�܂��͈��m��������̏n�c�Âʼnr�̂Ȃ̂ł���B�ǂ���Ƃ͂͂����茾���Ȃ����A�k�̓����Ƃ���A�����ɂ͒��R��i�Ȃ���܂���j������Ă���A�����͂����߂��ɉ͌����������B���̂�����̊ݕӂɂ́A���ł������������Ă���B�܂����m��������̕l�Ȃ���ΐ�͌��̊������A�n�c�Â̎��n���b粂ɐ̂͒߂����Ă����̂��낤�B �Ε��͖����Ə��������̂�����B������邱�Ƃ͂Ȃ��B�u�݂ȂƁv�Ƃ͐��ˁE����i�݂ȂƁj�̂��ƂŁA�͌��E�p�����Ӗ����Ă���̂ł���B�Ė��V�c��s���K�ꂽ�̂͌��݂̂Q�����ł���A�͌����p���ɂ͂����ɂ��������ȕ����������Ă����Ǝv����B�u�Ì�(��)�̍�v�͒n���Ɖ��߂���邩������Ȃ����A�u�Ì��v�͒Â��������т��C�݂ł���A�Ô��̂��Ƃł��낤�B���̐�[����ł���B���̍�͒��R�����ΐ�̉͌��Ƃ͌���Ȃ����A���̂�����̉����ɁA�C�ۂ̊����������t���Ă���l�q���r�������̂ł��낤�B���ꔼ��������̐�[���A������ʂ̓˒[�������̂�������Ȃ��B�̂͏�Q�������Ȃ���C������ł�������A����l����͈ĊO�A�߂��Ɍ��������Ƃ��낤�B �u�V���̔g�c�v�̉̂����l�ł���B��҂��K�������k�̓����̂ɏ㗤�����Ƃ͌��炸�A�n�c�Â���k�̓������]���ĉr�̂�������Ȃ��B�̒��ɂ��u�k�̓��̒�ɂ��āv�Ƃ͖��L���Ă��炸�A�u���Ē�Ɂv�Ƃڂ����Ă���B�Ō�Ɏ��́u�k�̓��v���ۂ�ƒu���Ă��邾���ł���B �q�ׂ͊������邪�A���̉̂��n�c�Âʼnr�܂ꂽ�Ƃ̓`���Ȃ�A�F������f�����������߂ɁA�Ė��V�c��s�̐����n���k�̓��Ƃ���ۚ������N�̌�����������̂ł͂Ȃ����Ƃ��l������B���m�������肪�k�̓��ł����Ă݂�A�n�c�Â��k�̗��Ƃ�����A�k�̗��ɂ���W�������n�c�É��҂̏��ƍl���Ă��闝�R�����������̂ł���B�������A�n�c�Âŋk�̓����r����Ƃ����āA�n�c�Â��k�̓��Ȃ̂ł͂Ȃ��B�Ή��Ən�c�Â͂ЂƑ����̊C�ݐ��ł���B����͔_�Ɠ��H�𑖂��Ă݂�����ɗ��������B�q��ʐ^������Έ�ڗđR�ł���B�n�c�Â̒�k�̓������]���ĉr�Ƃ��Ă��A���̉̂́u�k�̓��v���k���i�k���X�����j�̐Ή���n���w�����Ƃ͖����ł��낤�B �o�� ���̋k�̓��́A���͐Ή��_�Ђ̎Вn�ł��邩��A�Ή��̔����R�Ɛ��c�͂P���قǂ�������Ă��Ȃ��B���z���̏M�����̂�����̊C�݈�тɒ┑�������Ƃ͍l������B���m���̖k���A���̌Ð삠����ɂ��䏊���_�i������݂傤����j������A�V�q�V�c�̒��J�i���イ�Ђj�̂��ƂƂ��`�����Ă���悤�ł���B�ۚ������N�͌Ð�܂ŏn�c�Â̂悤�ɏ����Ă���B �����̂����ɈČ����ς܂��A�x�������A�ՋV�����s�����Ė��V�c�̈�s�́A�قǂȂ����̒n�𗣂�o�������Ǝv����B�u�D�悹�ނƌ��҂Ăv�Ƃ���A����͖�ɂȂ��Č����������Ƃ����悤�ɉ��߂���邱�Ƃ��������A�M���o���̂����瓖�R�A���V�̓���I�Ԃ̂ł���A���̓��͖�ʂ������o�Ă�����������Ȃ��B�������A�����ł��������ł��M�͏o���Ȃ��B���̌���̉��ŏ��������đ҂��Ă���ƁA�₪�āA��������������ɕς�鎞��������Ă����B����͂����炭���ł̂��Ƃł���A���V�̂��̎����ɏo���ł���悤�Ɍ����҂��Ă����̂��낤�B���̏o��҂��Ă���A�킴�킴�钆�ɏo�������̂ł͂Ȃ��B���̂��鐰�V�̖��҂��Ă����킯�ł���B���������łł���B�������ĐĖ��V�c��s�͐Γ��s�{�𗧂��A���i�݂��j�̐��c������m��������̑D���������Ƃɂ����̂ł��낤�Ǝv���B
�� �� �����s���q�̐Ė��V�c�`���Ɋւ��� �߂�
2009.01.10
��������������ƁA�l�b�g�Ŋ֘A�L�����Q�������܂����B�L�ӂȋL���Ǝv���܂��̂ŁA�Љ���Ă��������܂��B [�y�������q�Ɋւ������] ���Ύj�N���w�����s��ۖؑ��̗��j�x�ihttp://corikame.blogspot.com/�j�ɍڂ鎟�̋L���ł��B��ۖؑ��͐����s�ɂ���ΒȎR�[�̑��ł��B ���������X�̍H���Ƃ��V�q�V�c�y�������q�֍s�K�̂Ƃ��A�����㞊�E��b�͗Nj������q�̊ۓa�ɔ��܂�A���a����삵�A���i�_��ƂȂ�A��X�q��������11��̑��]�܈ʍH���R���S�ǂ̎q�H���S�Ƃ����v�N(1190�`1198)�\�B�R��1�ɑ�{�喾�_���R�鍑��芩�����ďZ�ݒ������B �v���q��̎q���Ɍn�}������B����͑�ۖؑ��̗��j�Ɋւ��钘��ł���A���q��n�c�Â̓`���n��ړI�ɂ����L���ł͂Ȃ������ɎQ�l�ɂȂ�܂��B [�n�c�ÂɊւ������] �u�_�ޔ��ɂ悤�����I�v�́u���x���Y�_�Ёv�̃y�[�W�ihttp://kamnavi.jp/ym/ajihayao.htm�j�ɍڂ鎟�̋L���ł��B���x���Y�_�Ђ́A���s�ߌ�����o���R���ڂɂ���_�ЂƂ������Ƃł��B �p�\�v���̌�A����y�����i�ƂȂ�����Β��b�ڈ́A���������_���ɗ\�����̏n�c�Â܂Œ���q�H���J�݁A�ΒȎR�n���z���ēy���ɓ��B���鍑�����J�킵���B�p�\�̗��Ƃ�����672�N�̂��Ƃł���A�Ė��V�c�̐����ƂقƂ�Ǔ�����̂��Ƃƌ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��ł��傤�B �ȏ�A�Q�l�܂łɒNjL�����Ă��������܂����B�ڍׂ͊eHP���䗗�ɂȂ��Ă݂Ă��������B �� �֘A�y�[�W �W�D�u���q�k�L��{�v�̐^�̒n�� �X�D�k�V�{�_�ЂƏn�c�Ñ� 10�D�Ñ�ɘ��̓��Ɠ��V�J �U�D�Ή��_�ЂƍՃP�� 17�D�䏊�_�� 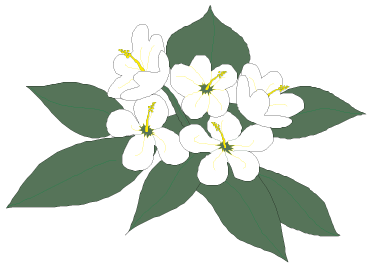 RELAX TIME RELAX TIME
|








![�n�c���]](../image/s_history/s_history7/s_history7_9.jpg)

