INDEX
|
10�D�Ñ�u�ɘ��̓��v�Ɠ��V�J �V.�̏n�c�Ì��z�ł́u�ɘ��̓��v�㉷��Ƃ��ď����Ă����B�����ł́A�Ñ�u�ɘ��̓��v�����㉷��łȂ������\���ɂ��ĐG��Ă݂����B ���㉷��͓��{�ŌÂ̓��H ���Q���̉���Ƃ����ΒN�ł��A���㉷��Ɠ����邾�낤�B����قǓ��㉷��̓|�s�����[�ɂȂ��Ă���B����ł͂ނ��A����ŊԈႢ�Ȃ��B�Ƃ��낪���Ȃ̂́A�w���{���I�x�ɏo�Ă���Ñ�́u�ɘ��̓��v�܂ł��A���㉷�Ǝv������ł���l�������ɑ������ł���B��ʂ̐l���������ł͂Ȃ��B���l���̋��y�j�Ƃ������Ȃ�A�Ñ�j�̐��Ƃ܂ł��A�قƂ�Ǘ�O�Ȃ������M������ł���̂ł���B ���ƂƂ����Ă��n���̏��͎��ɂ������Ƃ����邾�낤���A���̕ӂ͊������Ă��悢�B�������v�́A�N���ނ��� "����͓��{�ŌÂ̓�" �̃L�����y�[���ɕ����Ă��܂��Ă���Ƃ���ɂ���B�����M������ł���ق����b��i�߂��ł͊y�Ȃ̂ł���B�������g�A�S�̔������́A���̗�O�ł͂Ȃ��������A���㉷��͂ق�Ƃɓ��{�ŌÂ̓����낤���B �����M���闝�R ���㉷����Ñ�́u�ɘ��̓��v���ƐM�����ނɂ́A����Ȃ�̗��R������B���̈�́w�ɘ������y�L�x�핶�ɁA���̂��Ƃ��L����Ă��邱�Ƃɂ��B �ɘ��̚��̕��y�L�ɞH�͂��A���̌S�A�匊�����A���ĉ����p���āA�h�����Óߖ����������܂����~���āA�啪�̑����̓����A�����莝���x�藈�āA�h�����Óߖ���Ђ����������A�b���ԂɊ��N��܂��āA���R�����r���āA�u���b�A�Q�˂邩���v�ƞH�肽�܂ЂāA�H���т܂����ՙ|�A�������̒��̐̏�ɂ���B�}�āA���̋M��������Ƃ́A�_���̎��݂̂ɂ͂��炸�A���̐��ɐ]�}�ɐ��߂��ݐ��A�a�����₵�A�g�𑶂v�Z�ƈׂ���B �i�����c�̉E���ɔ�A�b���a�̉����ɑ��j�܂�A�����Ɂu���̌S�v�Ə�����Ă��邽�߁A���������S�̂��Ƃ��ƍl���Ă��܂��̂ł���B�Ȃ�قǁA����S�Ȃ瓹�㉷��ɑ���Ȃ��B����������́A�͂����ĉ���S�̂��Ƃł��낤���B�Ⴆ�u�ɘ��̓��̌S�v�̂��Ƃł͂Ȃ��̂��B����S�Ɓu�ɘ��̓��̌S�v�Ƃł͏ꏊ���قȂ��Ă��邩������Ȃ��B������ǂ̂悤�ɉ��߂��邩�́A�s���Ƃ����w�ɘ������y�L�x�̐����N����l�����ł��A���Ȃ�d�v�ȈӖ��������Ă���B �Ñ�u�ɘ��̓��v�́A���㉷��ɂ��炸 ���㉷�ŌÂ̓����ǂ����͂Ƃ������A���_�Ƃ��āA�w�ɘ������y�L�x�ɂ����u�V�c���̓��ɍs�K�i���ł܁j���ƍ~�i�����j��܂������ƁA�ܓx�i�����сj�Ȃ�v�̓��A���邢�́w���{���I�x�L���Ƃ���́u�ɘ������v�u�ɘ�����v�A�܂��R���Ԑl�̉̂ɂ���u�s�K���i���ł܂��ǂ���j�v�̂ݓ����A���̓��㉷��ł͂Ȃ��������Ƃɂ��āA�܂��A���R�������Ă��������B �ȉ��ł͗����āu�ɘ��̓��v�Ƃ��邪�A���̈ɘ��̓��́A�܂��A�V���V�c13�N�i684�N�j10���̓��C���C��n�k�ɂ��A���̂̉�������Ď~�܂��Ă��܂��Ă���̂ł���B����ɂ��Ắw���{���I�x�ɂ��u�ɘ��̓����v���ďo�Ȃ��Ȃ����i���ɘ�����v���s�o�j�v�ƋL����Ă���B�����n�k�œy���ł͒n�Ղ��L�͈͂ɒ������ĊC�ɂȂ�A��ςȔ�Q���o���Ă���B �ɘ��̓��̉�����v���āA�����̉���̖ʉe�͂��͂〈��ꂸ�A����ł����������͂ǂ��ɂ��ۂ��Ă������A�@��N�����Ă��ȑO�قǂ̗ǍD�ȓ��̏�Ԃł͂Ȃ������悤���B����ɑ����āA�V��17�N�i745�N�j�S���i�w�����{�I�x�ɂ�������Ă���j�̑�n�k�ɂ���āA����Ɍ��̎R�x������A�Ռ`���Ȃ����v���Ă��܂����̂ł���B �]���āA���̈ɘ��̓���684�N10���̎��_�ŁA���łɓV�c��́u�s�K���i���ł܂��ǂ���j�v�Ƃ��Ẳ���̎p�������Ă���A745�N�S���̎��_�ŁA���̓����܂ł����S�ɖ�����āA�Ȍ�r�p���A���̉���Ɖ����Ă��܂��Ă���̂ł���B������ɁA�����ό��n�Ƃ��ē�����Ă��铹�㉷�A�ǂ����āA���̈ɘ��̓��ł��邾�낤���B���R�Ȃ���A�w���{���I�x�Ɉɘ��̓����Ăяo�n�߂��Ƃ̋L�ڂ͂Ȃ����A�܂��A����Ȍ���A���w�ɂ͌���ēo�ꂵ�Ă��A���j���Ɉɘ��̓��̖��͓o�ꂵ�Ă��Ȃ����낤�Ǝv���B���̎�������A�㐢�̗��j�Ƃ͊��S�ɖڂ����炵�Ă���B �w�ɘ������y�L�x�̐����Ɠ���̉��� �����w�ɘ������y�L�x�ŋC�ɂȂ�̂́u�H�i�Ӂj���i�����j�т܂����ՙ|�i���Ƃǂ���j�A�������̒��̐̏�ɂ���B�v�́A���̈ꕶ�ł���B���ꂪ�ØV���畷�����̘b�ł����y�L�̈��p��(�w�ߓ��{�I�x)�̕t���ɂ����̂ł��Ȃ��A���ۂɕ��y�L�̐����Ҏ��g�����ď��������̂Ȃ�A�w�ɘ������y�L�x�́A�ԈႢ�Ȃ����̓��㉷��J����̐����ł���B�����āA���́u���̌S�v���A��̉���S�̂��ƂƂ��ċ^��͂Ȃ��B�h�ޔ�Óߖ��̋ʐ̓`���͍��̓��㉷��ɂ��`����Ă���A�����炭�A�Ñ�́u�ɘ��̓��v�ɂ�����̎��E�`�����A���㉷��̗��j�Ɏ�荞�܂�Ă�����̂Ǝv����B ���R�s�̓��㉷�J�����ꂽ�̂́A�Ñ�́u�ɘ��̓��v�����S�ɖ��v�����P�N�X������A�܂�V��18�N�i746�N�j12���̂��Ƃł������i���̔N�͂X�����[�ɂȂ�j�B����������S�́A���㉷�J������Ă����̌S���i�u���̕]�v��u���̌S�v�̒n���͈ȑO���炠�����悤���j�ł͂Ȃ����ƍl�����邱�Ƃ���A�w�ɘ������y�L�x���A�u���̌S�v������S�̂��ƂƂ��ď����Ă���̂Ȃ�A���̐����́A�����Ă��W���I���t�ȍ~�łȂ���Ȃ�Ȃ����ƂɂȂ�B
�ł́A���̌Ñ�́u�ɘ��̓��v�����㉷��łȂ���A����͉��S�ɂ������̂��낤���B ����Ɉɘ��̓��Ƃ����Ăऐ̂���ɘ��O���ƌ����āA�{�J����i�قɂ���j������A�ݐ쉷��i�ɂԂ��킨��j������B���̌S�ɂ��A�n�����炵�ĉ��炩�̉����݂�����������Ȃ��B�w�ɘ������y�L�x�̌̎��ɂ��Ă��A�����P�ӏ��̉���̓`���Ƃ͌���Ȃ��������ꂸ�A�����V�c�̉����̋{�Ƥ�Ė��V�c�̐Γ��s�{�i�����̂���݂�j�ł͖��̂��قȂ��Ă���B �������A����炪��������ł���Ƃ̉\�����܂߂āA�������Ă݂����B�����͂����_��S�i�������s��V���l�s�ɓ�����n��j�̂��Ƃł͂Ȃ����ƍl���Ă���B���̐_��S�i����̂̂�����A����̂���j�̒��ł������s�B�V���i���̂����j�ɓ��V�J�i��̂��Ɂj�Ƃ����Ƃ��낪����B���݂ł����V�J����Ƃ��������ȉ��P�������c�Ƃ𑱂��Ă��邪�A���̕ӂ�̒n�ɁA�Ñ�́u�ɘ��̓��v���������ƍl���Ă���̂ł���B���̗��R�������Ă��������B ���V�J�t�߂̒n�� �܂��A�n�c�Â̍��ł����������A���V�J�̒n�����ȒP�ɏЉ�Ă��������B
���V�J�͌��݂̐����s�B�V���ɂ���A���c�̐ΒȐ_�Ђɂ��߂��B����11�����𑖂�ƎR�ۂ̓c��ڂ̒��ɁA�ۂ��1��������̂����V�J����ł���B���K�͂ȓ��A�艷���h���{�݂�����A���悢���߁A���������l�C������B��A���J���P����ŁA17�x�̗���42�x�ɕ������Ďg�p���Ă���炵�����A����ł����͐s���邱�ƂȂ��N�o���A100�p�[�Z���g�|�������̓��ɂȂ��Ă���Ƃ̂��Ƃł���B ����{�݂̖k���͕��n�����A�쑤�͎R���}�Ζʂɗ������R��ɂȂ��Ă���A�����͌Ñ�̒f�w�ՂƎv���A����͒����\�����̐^��ł���B����𐼂։����ƍ��ꔼ���i�����Ȃ�͂�Ƃ��j������łقړ��㉷��̓���ɘA�Ȃ�B�����āA����ɉ�������ƈɘ����n���ĕʕ{����Ɏ���̂ł���B �w�ɘ������y�L�x�핶�ɁA��ȋM�������F������h�������悤�Ƃ��ĕʕ{�̓���n������������Ƃ̘b�����邪�A����́A���̒����\�����̂��Ƃ��w���Ă���̂ł͂Ȃ����낤���B �����\�����Ƃ����Ӗ��ł́A����͂��k�ɊO��Ă��邪�A�ʕ{�Ɠ��V�J�͂܂��������̐^��ɘA�Ȃ��Ă���̂ł���B���̒n�ɓ������牷�������Ƃ��Ă��s�v�c�ł͂Ȃ��n���I�����ł���B �V�۔N�ԂɈɘ������˂��Ҏ[�����w�������x�ɂ́A���V�J����̈ʒu�ɓ���i��ځj���������Ə�����Ă���B ���̒J �F�V�����̓��A���R��̓��ɁA���̒J�Ə̂��鏈����A����i�ꂢ����j�N�L�o�c�A⁁i���ȁj�̍L�T���O�ڋ��ɂ��āA�[�T�n�A��ԊƂ����ɁA��t�ɓ̓N������A���s�͂��āA��̒m�ꂴ�鏈����A�����i�Ђӂj�Ƃ��Đ����ɗO�N�A �i������̗����A�������̉����Ɋp�j�����˂̌S��s�i������Ԃ��傤�j�����ӂ��@�点�āA�����������牷���ɏo����Ȃ����ƒT���Ă݂����A�o����Ȃ������ƋL���Ă���B ���V�J�ƐΓ��s�{�`�� ���̓��V�J���ɘ��̓��ł͂Ȃ����ƍl���闝�R�ɂ͂��������邪�A�܂���������Ă��������B ����́A���V�J�̋߂��Ɉ��m���i���イ�j�Ƃ����Ƃ��낪����A���̒n�ɂ͐Γ������{�i�����͂��܂��j�̋��Ղ�����B�܂��A���̂��k���ɂ͋k�V�{�_�Ёi�����Ȃ�������j�̋��Ղ������āA���̗��Ђɏn�c�ÐΓ��s�{�̓`�������݂��邱�Ƃł���B�Γ������{�̖k���̔��n���版�ݕ��ɂ����Ă̓��O����i�ǂ�����ւ���j�́A�قƂ�ǂ��]�ˎ���ȍ~�Ɋ��ꂽ�V�c�n�т⍂�x�������̐V�Y�s�s�w��ɂ�閄�ߗ��čH�ƒn�тł���A���Â̊C�ݐ��͐Γ������{�t�߂̖k���ӂ�ɂ������ƍl�����Ă���B�Γ������{�͂��Ȃ�傫�Ȑ_�Ђł������ƌ����邪�A�V���̐w�i�H�ďG�g�̎l���U�߁j�ŐV���S�i���_��S�j���ӂ̎Ў��͂��ׂďĎ����Ă��܂��A�]�ˎ���̓V�۔N�Ԃɂ́A�w�������x�i1842�N�㈲�j�ɏ������K�ƒ������L����Ă���݂̂ł���B���̎Ђ��A��������ɋ߂��̋k�V�{�_�ЂɈړ]���āA���݂͂��̋����ɍ��J����Ă���B
�������A���̐Γ������{�ɂ͎��̂悤�ȌËL���c����Ă���Ƃ̂��Ƃł���B ���{�I�Ė��V�c�V�N ���������̒����������Б唌�C����D���Ƃ��āA ���c�P�Ƌ��Ɍ�D�ɂ��点�����A����������Ƃ����Y�̗l�Ȃ��A ���̐Γ��s�{�Ɍw�ŁA���Y�̋F��L�肯��ɁA��l�̑��P���ӁA �����đ唌�c���Ɖ]�����e�I�ɂ͂�₨�����ȉӏ������邪�A���̎ЋL�͂��Ȃ�Â�����c����Ă����Ǝv����B �܂��A�k�V�{�_�Ђɂ��̂���Ր_�R���̖ؑ́i�����͔��F�̈߂̓V�q���A���͏t�{�Ƃ̂��ƁB�����͂Ȃ����A�Ė��V�c�Ɠ�l�̍c�q���Ǝ@������j�A���тɌ����_��24�́i����32�̂�33�̂��������ꕔ���Ă����j�Ƃ����ؑ�������A������͐Ė��V�c�ߎ��̑��ƍl�����A���̂��������_���P�̂̎���͓���ł��Ă��Ȃ����A���̓����Ɂu�n�c�Ñ��k�v�y�сA�o���̖n�����F�߂���Ƃ̂��Ƃł���B ���̏n�c�Ó`���̐Γ������{���Ղ���A�킸���P�L�����x��̎R�[�ɁA���̓��V�J������B���̂��Ƃ���A�ɘ��̓������㉷��ƌ�����ꂽ���Ƃɂ��A�n�c�Â̗��j�܂ł�������ʂ֎����čs���ꂽ�\�����l�����悤�B�����낱�̒n���͓V���̐�ɏĂ���A�d�v�ȋL�^���قƂ�ǎc���Ă��Ȃ��̂ł���B�܂���ŏq�ׂ邪�A��������ɂ́A���ɂ����������R������B �ɘ��̓��Ɖz�q�� ���P��C�n�k��̈ɘ��̓��ɂ��ẮA�����V�c�̌��ɍ��i�i�c���@���C�j���ċ������݂����A�������������o�Ȃ������Ƃ����B �܂��A�����Q�N�ɂ��A�U�ʈɗ\����̉z�q�ʋ��i�������܂����j���A��a����S�������p�i����̂��Âʁj���}���čH�����s�����Ƃ̓`��������A�ǂ�Ȃ��̂�������Ȃ����A���p�͐̉��ɑ����̓����i�䂰���j������A�������肵���Ƃ���B����́u�ɘ��̓����v�ƌ����āA��ɑ������Ƃ�栂��Ŏg����悤�ɂȂ����B�[�R�ɓ����J�������A���̍H�@���}�f�łȂ��̂����āA�ʋ��͑傢�ɏ��p��M�����B�Ƃ��낪�A���p�͐ΒȎR���J���āA�_��i����Ă��A���Ō������̂��Ƃ��j����肽���Ɩ]�̂ŁA����͂�����댯���Ƌւ��A�l��f�킵��������Ƃ��Ĉɓ��֓������ɂ����Ƃ����B�ʋ����͂�݂����Ƃ̍߂ŋ��ɗ��Y�ɏ�����ꂽ���A�R�N�Ŗ��ߕ��Ƃ���Ĉɘ��ɋA�����Ƃ̂��Ƃł���B ���̘b���A���݂̐ΒȎR�̍���Ɍq�����Ă���̂ł͂Ȃ����Ɛ��@���邪�A���͐����E�������ɉ˂����Ă���̂ł����āA���R���ɂ���̂ł͂Ȃ��B���̏��p�͐ΒȎR�̊J�c�Ƃ���Ă��āA���V�J�߂��̑O�_���i�܂����݂��j�Βȑ��������̎Ёi���͌��݂̐ΒȐ_�ЎВn�ɂ������j���͂��߁A���̉@�E�ΒȐ_�ЁE���A�ЁE���i�悱�݂˂��j���A�݂Ȑ����E�������ɂ���B�C�s�m�ܑ̎R�������A�݂Ȃ�����̐l�ł���B���͏��R������ΒȃX�J�C���C���œy�����܂ł͏オ��邪�A�͓̂��O�����ΒȎR�n�̌����������̂ł���B
�Ƃ��낪�A���̌�ɂ��V��17�N�i745�N�j�̒n�k������A�ɘ��̓��̗��R�����āA����͍��x�͐Ռ`���Ȃ�������Ă��܂����Ƃ����B���V�J������ƁA���݂ł����̓`���ɂ҂�����̒n�`�ł���B ���̓��V�J�̏����͎R��Ƃ����B�R�����A�R�ۂ̈Ӗ����낤�B���̎R���̌q����ɒႢ���̉������������̂Ƒz�������B�Ƃ��낪�A���P�̓�C��n�k�Ȃǂɂ��A�R���̂��̓��̉����f�w�̂���Ȃǂɂ����̂��A����������͒n�Ւ��������̂ł��낤�B���̌�V���Q�N�i1533�N�j�ɂ͏n�c�Ñ��̖k���������ɂ���A�c�����N�i1596�N�j�ɂ͎s���𗬂����ΐ�ɂ������ꂽ�B�����̌��ʁA�N�����Ȃ��Ȃ蕽�R�������Ղ��A���̂��납�炩�A���V�J�Ə̂����̂ł͂Ȃ����Ǝ@������B���V�J�Ƃ������݂̒n�����A���ẮA�����ɓ��̉������������Ƃ��A�t�Ɏ������Ă���悤�Ɏv����B ���ɋʋ��̐Ղ��p���ňɗ\���� �ɂȂ����z�q�ʐ��i�������܂��݁j�́A�ɘ��̓������������Ƃ�傢�ɗJ���A�Ђ�����։��������ĎR��̐_�ɋF��A���̌��ʁA�_�̂������ɂ�蔭�������̂��A���㉷�ƌ����Ă���B�z�q�ʋ����z�q�S��̂��U�ʍ���̍��ɂ́A���̋ʐ��͉F���S�̑�̂��߁A���̌Z�̋ʎ�i���܂���j�͐_��S�ɋ��Z���Ă����Ƃ����B�����̉z�q���̊����̎�v�ȕ���́A�����i�������ʁj���瓹�O�i����V���l��y�����ʁj�ɂ���A����R��萼�̓�����ʂł͂Ȃ��������̂Ǝv����B �������ɁA����Ӗ��ł͈ɘ��̓��Ƃ������������݂������炱���A�V�c�炪�T�x�ɂ킽�肱�̒n��K�ꂽ�̂ł���A���ɘ����V�c�A�Ė��V�c�A�Q�l�̍c�q���̐����́A�z�q���̐��͊g��̏�ł��傫�ȈӋ`���������ɈႢ�Ȃ��B �ʐ��́A���̒��ŎR��̐_����u�������ő��ł���A�g���ł��锒�낪��ї����Če�����Ƃ���ɁA�K���V����������v�Ƃ̐_�ӂ�������A���̒n��T���āA���̓��㉷��������Ƃ���Ă���B���ꂪ���O�ɑ��݂����ɘ��̓��̗��j���猩�����̓��㉷��̔���杂ł���B���{�����̔����`���̂悤�����A����͖쒹�ł���ƂƂ��ɁA�R��̐_�̌���Ƃ����ꂽ�̂��낤�B ����Ɠ��l�̓`�������݂̓��㉷��ɂ���B�u���ɏ�������H�̔��낪��Ԃ��畬�o���鉷��������A�������ł��Ă��̒��ɑ���Z���Ă����Ƃ���A���͊��S�ɖ����Ă��܂��A���C�ɔ�ы������B�i���㕨��j�v������T���Ă݂�Ɖ����������A�Ƃ������̂ŁA���ꂪ���㉷��̔����Ƃ���Ă���B�����Ă����炪�A���㑤���猩������a���̗R���ł���B���̔���Ƃ́A�ɘ��̓��������ď������z�q�ʐ��̐S���̂��̂ł͂Ȃ������̂��B���̈Ӗ��ł͂��̔���`���́A�h������ɘ��̓��̏I���ƁA�V�������㉷��̒a�����ے����镨��ł��������B���̌�A�ʐ��͓��㑤�̕����S�i�ɘ��k���A���ݏ��R�s�j�͖̉싽�Ɉڂ�A���㉷��̊J���ɓ��������B���ꂪ�A�z�q�n�͖쎁�̎n�܂�Ƃ���Ă���B�����āA���̋ʐ��̈ړ��ɂ��z�q���̊����̎�v�ȕ��䂪���O���瓹����ʂɈڂ�A���ƂȂ������O�̈ɘ��̓��̗��j���A�z�q��͖쎁�̗��j�̒��ŁA���㉷��̓`���Ƃ��đg�ݍ��܂�Ă��������̂Ɨ������Ă���B ���㉷��̒a���͉͖쎁�̗��j�̎n�܂肻�̂��̂ł���A��ɓ��㉷��̑���ɓ��z��i��Â����傤�j��z�����̂��A���㉷�͖쎁�a���̏ے��I���݂ł��������炾�낤�B�����Ă����ɁA���݂̈ɍ����g�_�Ёi�����ɂ͂���j�����c���ꂽ�̂ł���B����ȑO�̈ɍ����g�_�Ђ́A��������̎R�[�̕��ɂ����������Ȑ_�Ђ������Ƃ���Ă���B�Ր_�͔����_�R���ŁA�_���c�@��̓`�����猩�Ă��A�����̐Ή��_�Ёi���킨������j�Ƒ������Ă���B�Ή��_�Ёi�����{�j�ɂ͐_���c�@�̍ՃP���`���������āA�ɍ����g�̉��Ƃ̐����ꕔ�ɂ���B�܂��A�ɋ���̉��͈ɑ]�T�_�ЂƂ̐�������A���̉��蕶�̈Ɏ�玔g�̉���A�Ԑl�̉r�ɋ���̉��̖����A�z�q���Ƌ��ɓ���ֈړ����Ă��܂������Ƃ��l�����悤�B �ܓx�̍s�K�ɂ��� ���ɓV�c���̂T�x�̍s�K�ɂ��āA�l���Ă݂悤�B �@�w�ɘ������y�L�x�핶�ɂ́A�ŏ��Ɍi�s�V�c�Ɣ�����P�c�@�̍s�K��������Ă��邪�A�w���{���I�x�ɂ��ƌi�s�V�c�͋�B�ɉ������Ă���̂ŁA���˓��C���q�s�������Ƃ́A���Ԃ�ԈႢ�Ȃ����낤�B�F���V�c�E�Ė��V�c�̎���ɂ͉F���S�Ɉ������̖�������A�������͒n�������ł͂Ȃ��ɂ��Ă��A�i�s�V�c�̎���ɂ��A���̕ӂ�Ɉ������̈ꑰ�����Z�������Ƃ͍l������B�i�s�V�c�̍c�q�A�����Õʖ��i�������ɂ���킯�݂̂��Ɓj�������V�c�̌��ɐ����̈ɑ]�T�_�Ђ֓����čc�Ђ��O�߁A�䑺�ʁi�݂ނ�킯�j�̑c�ƂȂ��Ă��邱�Ƃ��l������ƁA���̕�ł��鈢�����؎��i���ׂ̂��������Ɓj�̏����c�P�i�������Ђ߁j�͂��̕ӂ�̏o�g�������ꂸ�A�����Õʖ��Ƃ̌q���肩��l���Ă݂Ă��A�i�s�V�c�������̒n�֗���������\���͏\���ɂ���B �A�Q�Ԗڂ̒����V�c�ƍc�@�́A�ѐϐ_�Ёi�����Â݂���j�t�߂̟J�Ái�������Áj�ɒ��D���s�{���\�����`��������A�ѐϐ_�Ђ̍Ր_�T���̒��ɂ͑ђ��ÕF��������є䔄���E�\��ʉ��炪�J���Ă���̂ŁA����͖�肪�Ȃ��B �B�R�Ԗڂ̖@���剤�i��{�����c�q�j�ɂ��Ă̓`���͌��݁A�����Ɏc���Ă��Ȃ��B�������n���́A�ʒu�I�ɐ̂��猹�����k���Ȃǒ����̔e�������Ɋ������܂�₷���A�͖�E�א�E�O�D��ɂ�鑈�����������B�Ƃ�킯1585�N�̓V���̐w�ł́A�V���S�𒆐S�ɖ{��E�o��E�Ў��Ȃǂ��H�ČR�i������E�g��j�̐�ɂ�����A�M�d�Ȓn���̕�����Y�ł���ËL�E�����̗ނ����������D�ɂ���Ă���B�����̎ЉƂ̋L�^�ɂ��u���̎��ЁA���Ǝc�炸�Ď����ĂȂ��v�ƋL����Ă���قǂł���B�����āA�����̓`���Ǘ��҂ł�����E�{�i�E�m���Ȃǂ��A���Ƃ��Ƃ��������ɂ��Ă���B�łɑ����Ă��܂������j�������͂��ŁA�������q�̍s�K�ɂ��Ă͂������Ƃ��Ȃ������Ƃ������Ȃ����A�u���̉��v��u�Ɏ�玔g�̉��v�̏ꏊ�����n�Ŕ��ł���A�@���剤�̍s�K�ɂ��Ă������Ɨ�����邾�낤�B �ق��ɂ��A�������q�̊W�Ō����A�����s�������ɂ���l�����\���J����61�ԎD���������i�������j�́A�������q���p���V�c�̕a�C�������F�肵�đn�����ꂽ�Ɠ`������B�܂��A�����̌Ù��A�@�����i�ق����j�̑n�������ォ�Ƃ����A���~�i����Ӂj�̍����O���䎁�ɂ��Ƃ̌��������邪�A�������q�̖��ɂ��A�z�q�v�Z�i�����܂��݁j�����������Ƃ��`�����Ă���炵���B �w���{���I�x�ɂ́A���ÓV�c�̂Q�N�i594�N�j�A�V�c���c���q�i�������q�j�Ƒh���b�ɏق��āA�����̋�����}��ꂽ�Ƃ���A���̂Ƃ��A�����̐b�E�A�炪�����Ď������ƋL����Ă���B���̓����̖@�����͎l�V�������̑傫�ȉ����ƍl�����Ă��āA���̊����܂łɂ͂��Ȃ�̔N����v�����悤�����A�@���剤�̈ɘ������i596�N�j�͂�����������@���������Ɗ֘A������A���̉��蕶�ɂ��Ă��A��������ɉz�q�v�Z�炪���Ă����̂ł͂Ȃ��̂��B �C�����V�c�ƍ��P�c�@�ɂ��Ă����݁A�����ɓ`���͎c���Ă��Ȃ����A�z�q�S�i���ݍ����s�j�ɂ͂���悤���B����ɁA�n�c�Ñ��̈��m���ɐĖ��V�c�������̐Γ��s�{�`�������邱�Ƃ���@���Ă��A�ȑO�ɂ������ɗ�������Ă����\���͑傫���ƌ�����B �����s�щ��i���������j�̉����X���i�������肶�j�ɂ́A�u�����V�c�����㉷��i�܂��ɘ�����Ƃ̓`��������j�֍s�K�̓r���A����i�Ђ����Ȃ��j�Ŗ\���J�ɑ����A���n�ɔ������߁A���̖����t�����v�Ƃ̓`�������邻�������A�����V�c�͓��㉷��ł͂Ȃ��A�����̏n�c�ÐΓ��A���邢�͓ݐ쉷��E�{�J����֍s�����Ƃ����̂ł͂Ȃ��̂��B�u���㉷��v�̌ŗL���͈ӊO�ƐV�����A�]�ˎ��゠����Ɏn�܂�ƕ����B�ɘ��̓��㉷�ƌ㐢�̐l�����Ⴂ���āA���������\���ɂȂ����̂ł͂Ȃ����낤���B�����V�c�̎���ɂ́A�������̒n���ȂǂȂ��A���㉷�̂��̂����݂��Ȃ��̂ł���B �D�Ė��V�c�Ɠ�l�̍c�q�́A�ނ��A�n�c�Âɗ��Ă��邾�낤�B �����A���V�J�̐Γ����������ꂽ�Ƃ��Ă��A�ɘ��̓��Ƃ��Ă̖{�J�����ݐ쉷��Ȃǂ��c���Ă����Ȃ�A�z�q�ʋ���A�ʐ��́A����Ȃɂ��^���ɉ���̕�����ؖ]���Ȃ�������������Ȃ��B���������������̂ͤ���̓��V�J�̐Γ����A�ق��Ȃ�ʁu�s�K�|�v�Ƃ��Ắu�ɘ��̓��v���̂��̂���������ł͂Ȃ��̂��낤���B���̂��Ƃ͉����ɂ���Č��肳�����̂ł͂Ȃ��B��Âɋ߂��A�����R���X�����A���ɗ���ΒȂ̎R����ԋ߂ɋ����邱�Ƃ��o����A�n���I�����̔����������ł����������炾�낤�B�����āA���������̏�̒��]�̊J�����Ƃ���Ɉʒu��������ł���B �Ԑl�̖��t�� ���ɁA�R���Ԑl�̉̂�ǂ�ł݂����B �R���h�H�Ԑl�A�ɘ��̉���Ɏ���č��̈�� ��ɒZ���Ԑl�̐��v�N�ɂ��Ă͕s�ڂƂ���Ă���B��̔N���̕�������̂́A�_�T���N�i724�N�j����V���W�N�i736�N�j�܂łƂ̂��Ƃł��邩��A�����V�c�̎���ł���B�����̋{��̐l�������ƌ����邪�A����ȑO�̂��Ƃ͕������Ă��Ȃ��B�����A�R�㉯�ǂ�唺���l��Ɠ�����̉̐l�炵���Ƃ͌����Ă���B�܂��A���̉̂ɂ��Ă͐_�T�N��������̍�ł͂Ȃ����Ƃ������邻�����B �������A�傢�ɖ�肪����B���̉̂ͤ�Ԑl�������u�ݓ��v�̑O�ɗ����A���ۂɎ����Ŋm�F���ĉr��ł���̂ł���A�̂̓��e���炵�Ă��V�c��̍s�K���ꂽ�ɘ��̓��ł��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ����낤�B�Ƃ��낪�A���̓V�c��̈ɘ��̓��͓V��13�N�i684�N�j10���ɓ�C�n�k�ŕ��A���v���Ď~�܂��Ă��܂��Ă���̂ł���i���ɘ�����v���s�o�j�B��k�ł�����A���Ƃ����̕��o���߂����Ƃ��Ă��A��U��v�����ȏ�A���łɉ����̓��r����͂̌��`�͗��߂Ă��Ȃ��͂��ł���B�Ȃ̂ɁA���̉̂�ǂނƁu�b�̖� ����㋂��ɂ��� ������ �߂��̂炸�v�ƁA�̂ƑS���ς���Ă��Ȃ����̂悤�Ȉ�ۂł���B �܂�A���̉̂��Ԑl�̑z���Ɋ�Â���z�łȂ���Ƃ��������t�������A���̉̂̍�̔N���́A�V��13�N10���ȑO�ɂȂ炴������Ȃ��̂ł���B���Ƃ��A�Ԑl�̐��N���R�㉯�ǂ�Ɠ���660�N���Ɖ��肷��A�Œ��ł�24���炢�̎��̍�̂ɂȂ�B�u����ȃo�J�ȁv�ƌ����Ă��A�Ȃ���̂͂Ȃ�̂ł���B���̏ꍇ�A�V���W�N�i736�N�j���Ԑl�Ō�̍�̔N�����Ƃ���A76�Β��x�ɂȂ��Ă���B�������A660�N�̐��N�͉���Ƃ��Ă̘b�Ȃ̂����B �ɘ��̓����n�k�ōŏ��Ɏ~�܂����̂�684�N10���B���̓��㉷�J�����ꂽ�̂�746�N12���B���̊ԁA�ɘ��̓������Ƃ������͕ۂ��Ă����̂��낤���A���̉̂ɂ��鉝���̉���̖ʉe�́A���̎����ɂ́A���͂⑶�݂��Ȃ������͂��ł���B�z�����z�łȂ�����A�����V�c�̎���ɐԐl���r�߂�͂��ȂǂȂ��̂ł���B�Ȍ�A�V�c�炪�ɘ��̓���K�ꂽ�C�z�������Ȃ��̂́A�����]�̔s�k�ɂ�荑�傫���]���������������ł͂Ȃ������B���Ƃ��������Ă��u�ݓ��v���̂��̂����݂��Ȃ��̂�����A�����Ȃ������̂ł���B �Ȍ�A�����܂ŕ��w���ɓo�ꂷ��ɘ��̉���Ƃ����A�݂ȓ��㉷��̂��ƂɂȂ�B���̓��㉷��ł���A�L���ł͂��������A�����̂悤�ȗ���������Ɏ������̂́A��������ɂȂ��ē��㉷��{�ق����Ă��Ă���̂��Ƃ��Ƃ����B�����āA���̓��㉷��̗��j�̒��ɁA�Ñ�́u�ɘ��̓��v�̓`�����g�ݍ��܂�Ă��܂��Ă���͂��ł���B ���̉��Ǝˋ���̉� �R���Ԑl�͂�����������A�Ⴂ����e�n�𗷂��ĕ������̂ł͂Ȃ����낤���B���̂��Ƃ���̗D�ꂽ���i�́i�ƌ������A���͏���̂ł�����j�ނɎ���������ƂȂ��Ă����̂�������Ȃ��B �����v���Ă��̉̂�ǂނƁA�G�̂ł͂��邪�A���ƂȂ���X��������������B�܂����R�ɋZ�I���Â炳��Ă��āA����ȉ��߂͒N�����Ȃ���������Ȃ����A�|���i�������Ƃj����������������悤�Ȃ̂ł���B���Ƃ��u�~���܂��i�����߂ɂȂ��Ă���������j�v�Ɓu��鋏�܂��v�A�u�����������i�ł܂��Ă������Ă���j�v�Ɓu�_�X�����v�ȂǁB�����l���ēǂނƁA�u�ˋ���v���u���v�ł���B �ׂ��������A�u�ˁv�͐ړ���E����ŁA�u���v�͐���A�u��v�͐_���}����_�Ղ�̏ꏊ�ȂǂƂ��������ɂȂ邪�A�v����ɐ_�X�����ɘ��̍���̘[�ɍL���闢�̂��Ƃ��r���Ă���̂��Ǝv���B�u��v�́u��v�̈Ӗ��Ƃ����邩��A�L�`�ɂ͗���ΒȎR�n�̘[�ɍL���闢�u�_��v���Ӗ����Ă���Ǝv����B���ɐ_��̏n�c�Â���k�̒n��́A���R�Ɠ��]�̊Ԃ���������1�L������Ȃ��Ǝv����ג����n�`�ł��邪�A�ΒȘA�M��_�̎R�Ƌ�����_���ȗ��ł���B�_��̒n�������X�����ɗR�����Ă���̂��낤�B �܂��A�u���v�͂��̕ӂ��т̊C�ݐ��̂��Ƃ��w���̂��낤���A�ŗL���ƍl����u�u���v�ɂȂ�A�u�ˋ���̉��v�́A����n�̂��ƂƂ��l������B�����A�����̊C�ݕ����猩���ΒȎR�n�͗Y��Ŕ��������A�ɑ]�T�_�Ђ̒����O���������ΒȂ̗�͕x�m�R�̒���̂悤�ŁA�����ɂ��u�����������v�Ƃ��������ł���A���ƂȂ����|�������̂�����B�f���ɓǂ߂A����͈ɑ]�T�_�Ђ̉��̂��Ƃƍl������Ȃ��B
���������́A�ɑ]�T�_�Ђ̂������n�ɁA�͂����ĉ��������̂��Ƃ����_�ɂȂ�ƁA����́A���������������������Ȃ��B���A����́u�̎v�� 熎v�͂����v�̏ꏊ���u�ˋ���̉��v�ł���A���̉��Ƃ͕ʂł����Ă������̂�������Ȃ��B �����A�����ɂ́A�Ԑl�͉̉̂��x�ǂ�ł݂Ă��A�u�ݓ��v�̂���ꏊ���A�u�ˋ���̉��v�Ɠ����ł���Ǝv���ĂȂ�Ȃ��B�]���āA���́u�ˋ���̉��v�͌ŗL���Ƃ͌����Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ƃ��l���Ă���B���̉̂́u�ˋ���v�́u�ɘ��̍���v�ɑ����Ă���̂ł����āA�K�������u���v�̂ق��Ɍ������Ă���Ƃ͌���Ȃ��B�܂�u�ˋ���̉��v�́A�_��ɂ��鉽�����̉��̂��ƂŁA����̉��̂��Ƃł͂Ȃ����ƍl���Ă݂����B���̉����̂��u�ˋ���̉��i�_��̉��j�v�Ȃ̂ł���B�]���āA�ŗL���Ƃ͌���Ȃ��u�ˋ���̉��v�́A���ɂ������Ă����̂��ƍl���Ă���B �Ⴆ�Γ����_��̗��ł����Ă��A�Ԑl�̉̒��́u�ˋ���̉��v�ƁA���̉��蕶�́u�Ɏ�玔g�̉��v�́A�܂��ʂ̏ꏊ�Ȃ̂�������Ȃ��B���R�s�ݏZ�j�Ƃ̍��c�m�ꂳ��Ȃǂ́A���̉��蕶�́u�_��v�ł͂Ȃ��Ñ�̗N���E�쐅�̂��Ƃ��Ƃ��āA�u�Ɏ�玔g�̉��v�͐����s�X���i�Ђ݁j�̐Ή��_�Ђł͂Ȃ����Ƃ��������o���Ă���ꂽ�B�߂��ɂ͒��뉷��i�����肨��j������A�Ή��_�Ќ��{�i�̋ʈ�Ƃ̉��~���ɂ͌Ñォ��̈�˂������āA�ʃm��Ə̂������Ƃ���A�{�i�Ƃ̐����I������ʈ䎁�ɉ��߂������ł���B�_��̏ꏊ�͕ʂɋ��߂Ă����邪�A���뉷��i����삪����A���͂������ƌ������Ƃ����j�̋߂��ɂ���̂œ��̉��ƌĂ�A���̉��͓������̂��ƂŁA���ꂪ���퉪�ƕς��u���킨���v�ƂȂ����ƍl����A���̉\��������B�Ή��_�Ђ̉��ɂ͐_���c�@�䂩��̍ՃP��������A���̒n���ʈ�Ƃ̓��̉��ɑ��đ���̈Ɏ�玔g�̉��Ɣ�肵�Ă��悭�A���R�̈ɍ����g�_�ЂƂ̋��ʐ����M����B �������A�R���Ԑl�̉̂Ɍ����Č����A���́u�ˋ���̉��v�́A�B�V���̓��V�J�R�̎R���ɂ��đ��݂����ł��낤�Γ��̉��̂��Ƃł͂Ȃ����ƁA�����ł͍l���Ă���B�����ɌÑ�́u�ɘ��̓��v�����݂����̂ł͂Ȃ����낤���B�@���剤�炪�k���i�s���X���E�k�j���ʂ��ꡂ����Ƃ��Ă��A�ɘ��̓������V�J�ł���A�ԋ߂Ȃ̂ŁA�ɘ��̓���K��Ă������Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B���̂悤�ɁA���̉��蕶�̌����ꏊ���ɑ]�T�_�ЂȂ̂��A�Ή��_�ЂȂ̂��A���V�J�̐Γ��̉��Ȃ̂��ɂ��Ă͕s���ł���B�Ή��_�ЂȂ�ǂ����Ɏc����Ă��邩������Ȃ����A���V�J�̓��̉��������Ƃ���Ή�v�����̂ŏo�Ă��Ȃ����A���邢�́A�M�d�Ȕ蕶�͌@��o����Ĉړ�����Ă���\��������B�ɑ]�T�_�Ђł��A�ɘ��̓����r�p������͔蕶�͖��p�Ȃ̂ŁA�z�q�������R�̓��㉷��։^��ōs������������Ȃ��B �Ԑl�̉̂Ɠ��V�J�̒n�` �u���R�� �X�������v�Ƃ���̂��A�_��S�̌i�ςɂ҂�����ł���B�ΒȎR�n�͂������A���ꂽ���ɂ͂��܂Ȃ݊C���̌|�\�����i�����悵��Ƃ��j�܂ň�]�ɏo����B���R�s�����͔��������Ǝv���邪�A�R�܂ŋX�i���j�������ǂ����܂ł͕�����Ȃ��B���R�͈��Q�ł͓s��Ǝv���Ă���̂ŁA���܂ɓ��㉷��܂ōs���Ă��R�ȂǒT���Ă݂����ƂȂ����A���㉷��ɘ��̍���͂������āA�_�X���������Ɍ����邾�낤���B ���Ɂu�ݓ��̏�� ���Q�i���ނ�j������v�ł��邪�A�S�W�Ȃǂ̖�����ƁA�����Ă��u����̂قƂ�̗сv�Ƃ��Ă���B�ԈႢ�Ƃ͂����Ȃ����A����ł́A�ق�Ƃ��Ɂu�ݓ��̏�̎��Q�v�ɂȂ邾�낤���B����͎��Q������ɂ������̂łȂ���Ȃ�Ȃ��B�܂�A�Б����R�̊R�������̂ł���B�ݓ��̂قƂ肩���ɂ���R�̎��Q�����グ�Ă���̂ł���B
�u�b�̖i���݂̂��j�v�ɂ��Ăͤ�ɂ����m�Ƃ�����A�s�ڂƂ��Ă�����̂�����B�L�����ɂ����m�Ƃ��邪�A�ق�Ƃ��ł��낤���B�܂��A���̉ӏ��́A�Ԑl���w�ɘ������y�L�x��O���ɒu���Ă��邩�Ƃ�������Ă��邪�A�ɘ��̓��㉷��Ƃ��Ă���w�ɘ������y�L�x���A�Ԑl���m��@��͂��蓾�Ȃ������͂��ł���B���n��K�ꂽ�̂Ȃ�A�̎����炢�͒m�肤��͂��ł���A�����V�c�́u��a�˂̖v�Ƃ́A�܂��ʂł��낤�B ��z�̏ꍇ�� ���̉̂��A�Ԑl���Ⴂ����ɍ�����̂Ȃ̂��A��z�ɂ����̂��́A���̂Ƃ���悭������Ȃ��B�������A�Ԑl�͎��ۂɂ��̒n��K��Ă���͂��ł���B���̂Ƃ����������Ƃ𗦒��ɉ̂ɉr�ݍ���ł���̂ł���A���邢�͉�z�ł���A���ɂ�����ł��������̂�������Ȃ��B ������z�̉̂��Ɖ��肷��A�Ԑl�͈ȑO�K�ꂽ�ɘ��̓�����v���Ď~�܂������Ƃ��m���Ă����ɈႢ�Ȃ��B�u��������~���т䂩�ށv�Ɖr��ł���B����́A���͌��ƂȂ������Ƃ𗝉�������ł̍�҂̊�]�ł������Ƃ��~�߂���B�܂��A��̔N����684�N�ȑO���Ƃ���A���̂ɂ���u�O�c�Áv�̔N����́A�܂�20�N���܂肵���o�߂��Ă��Ȃ��B���Ƃ��Z�I�I�\����p�����ɂ��Ă��A�܂��Y���قǂ̔N�ł͂Ȃ��Ƃ������悤�B�Ƃ��낪�u�D�悵���ޔN�̒m��Ȃ��v�ƁA�����Ԃ�N�����o�����悤�ȕ\�����Ƃ��Ă���B���̈ꌩ���肰�Ȃ��r�����܂ꂽ�r�Q�̌��́A�h������`�i��܂Ɓj�E����ւ̈��ɂƂƂ��ɁA�����̎��Ԃ̌o�߂����Ӗ����Ă��錾�t�Ȃ̂�������Ȃ��B���̏�ŁA���ƂȂ����ɘ��̓��݂̍肵���̋P���ɉi������^���Ă��������ƁA���̉̂���������Ƃ��l�����悤�B������ꏊ�܂ł�����ł�����@�ŁA���̉̂��c���Ă���悤�ł���B ���́u�s�K�|�v�Ƃ��Ẳh���ɕ�܂ꂽ�Ñ�́u�ɘ��̓��v�̎p�́A�w�ɘ������y�L�x�ł́A���㉷��̗��j�̒��ɑg�ݍ��܂�Ďc�����B�����̓`������j��m���ŁA���̈핶�͋ɂ߂ďd�v�ł���B�������A�R���Ԑl�̉̂̒��ł́A���ɐ��̂܂܂ł��̎p���r�����܂�Ă���B����́A�����Ō��n�ɗ����A�͂�����Ɓu�ݓ��v�̎p�����Ă�������r�߂�̂ł͂Ȃ����낤���B���̏ꏊ��m���ŁA����ȏ�̂��̂͂Ȃ��B ����� �ɘ��̓��͈�U�A�r�p������A���̂��납�炩�A�܂��z�N���o�������̂Ǝv����B�������A�x�d�Ȃ�n�k�ŗN�o����}�O�}�̈ʒu���ς�������߂ɁA���ɂȂ�����������Ȃ��B ����������悤�ȓ`�����c�邪�A���Ƃ͉�����̂��Ƃ��w���Ă���̂��ɂȂ�ƞB���ł���B �����V�c���Ė��V�c�����������͓̂~�ł��顕��ʂɍl���āA�����ē~�ɗ��ɓ���ɗ��邾�낤���B���a�Ɉ������Ƃ��Ă��A�����ė��т�����̂ł͂Ȃ��B�������ɂ��Ă��{�C���[���Ȃ�����ɁA�c����ߎ��̕��܂ŁA��ʂ̓����ǂ̂悤�ɂ��ĒZ���Ԃɕ������̂ł��낤���B�C���z���Ă܂ł킴�킴�������ɗ��邮�炢�Ȃ�A�Ƃōs���ł����Ă����ق����������낤�B�w�������x�ɂ����͗N�����Ό��\�����邪�A������ꕨ�ɗp����̂͂悭�Ȃ��Ə����Ă���B����ɕʕ{�̓����������̂ɁA������Ƃ�����A���������̂ł͂Ȃ����B�w���{���I�x�ɂ��u�ɘ������v�u�ɘ�����v�Ə����Ă���̂�����A��͂�A�����͉������Ɖ��������B �������A���R�Ɩ������̓���]�Ƃ������łP�L���قǂ�������Ă��Ȃ��u���R�̋X�������v�̉��̏�ł���B�������ɓc�ɂł͂��邪�_�X�����A�i�ρE���Ƃ����Q�̒n�ɁA���̈ɘ��̓��͂������̂ł���B ���Âقǂ̋K�͂ł͂Ȃ��ɂ��Ă��A�r�p����A�܂������ɍz�o�n�߂��B���ꂪ�Ñ�ɘ�����̖��c�ł�����A���݂̓��V�J���Ɨ������Ă���B�吳���N�Ɍ��O���ꂪ�J���ꂽ�Ƃ̂��ƂŁA17�x�̓������Ă��邪�A�Ƃǂ܂邱�ƂȂ��N�o���A�|���������Ƃ����B1300�N�]�̎����o�Ă��A�݂肵���́u�ɘ��̓��v�̎p��f�i�����Ă������̂ł���B �n�c�ÐΓ��Ƌk�̉� �������������A�k�V�{�_�Ђ̎ЉƂ̌��`���L�����j��������@�����A���܂��܁A���̈ꕶ���ڂɕt�����B �k �����̎j���́A�V���̐w�Ō×��̎ЋL���Ă��ꂽ���߁A�Ȍ�ɑ�X���`�Ƃ��ē`���Ă������̂��A����12�N�i1727�N�j6��23���ɁA�������������̂̂悤�ł���B ��͂�A���̓��V�J�̎R��ɂ́A�����������̂��B �Ƃ���ŁA���̎ЉƂ̌��`�̒��ɂ́u�k�V���Γ���v�̈ꕶ������B�����Ō����k�V���Ƃ͐Ė��V�c�̂��Ƃ��낤���A�Γ��������ɂ��ẮA���낢��Ƙ_�����Ă���B���ɂ͐Ε��C�i�����Ԃ�j�ł͂Ȃ����Ƃ̐�������悤���B�Ε��C�ͤ�ȒP�Ɍ����Ύ��R�̓��A�𗘗p�����������C�̂��Ƃł���B�������A�Ε��C�͈�ʂɉĊ��̂��̂ŁA�Ė��V�c��s���n�c�Âɗ��܂����~���ɐΕ��C��͓̂����ɍ����Ă��Ȃ��B�����ŁA�u�X�D�k�V�{�_�Ёv�ɂ����鐄�_�̂悤�ɁA�����̋k�L��{�ł̏o���������Ђ̌��`�Ɍp������Ă���ƍl����ƁA�Ė��V�c�������������q�̉ĂɁA����ɐΕ��C�������Ƃ��w���Ă���Ƃ��z������悤�B �����������́A�����炭�����ł͂Ȃ��āA���̂悤�Ȃ��Ƃł���B ���̉����畽�n�֗��ꉺ��������̗]�����A�����ȓ��]�ɒ������މӏ�������A���̓��]�͔��i�̌`�����Ă����̂Ŕ��i�ƌĂ�Ă������A���ΐ�̈ꗬ�������ɗ��ꍞ��ł����B���̓��̐�̏o���̋߂��̐Γ��̍�̖،��i�����̖��������̂��낤�j�ƌ����Ƃ���ɁA�Ė��V�c���~�藧���A�s�{��������̂ł���B�������V���̖،��Ƃ��Ă��ꏊ�ŁA���������������̖��A�����Ă���B���Ȃ킿�A���݂̋k�V�{�_�Ћ��Ղ̒n�ł������B���̂Ƃ��V�c���A���i�֒������ޓ��̗��o���̏�����ň͂킹�āA�l�H�̘I�V���C�������̂Ǝv����B���ꂪ�A�����Ō����Ƃ���̐Γ��ł���A���̏�̈ɘ��̓����̂��R�ۂɂ���Γ��ƌĂꂽ�̂ł͂��낤���A��q�̗��R����A�Ƃ��ɂ������Ė��V�c�̐Γ��s�{�Ə̂��Ă���̂ł���B ����͎����������Ă��邾���łȂ��A�k�V�{�_�ЎЉƂ̌��`�ɂ���������Ă���̂ł���B ���݂ɏn�c�Ï��R���ł́A���㉷����ӂɐ��ӏ��̏n�c�Ì��n���������Ă��邪�A�ɘ��̓��̗]���������ĊC�ɒ����ӏ�������A�C�܂ł̋������Q,�R���Ɓw���B����L�x�ɏ�����Ă���Ƃ��납��A���㉷��Q,�R���i�P���͂U���j�̋����ɂ�����n�̂ق����L���ƍl�����Ă��邻���ł���B ���B����ҁA��������≗�V����A�������l������A���X�o������R����A�D�X�����C����A���ꔒ�����A�l���ݎA���@���A熃��C��O���A�i�����c���R�`�ɂR�̉����Ɏ����邢�A����_�̃V���j���E�ɑ䁁������j�������A���̓��e�͏�q�̂悤�ɋk�V�{�_�ЎЉƍ����Ƃ̌×��̌��`�ƉZ��ł���A�܂�w���B����L�x�̂��̕����́A�����̈ɘ��̓��Ən�c�Âɂ��ċL���Ă���̂ł���B�ɘ��̓��ƌ����Γ��㉷��ƍŏ�����v�����ނƂ��납��A����Ă�����ł����낤�B�����̎������A���㉷��t�߂̊C�݂ɂ����瓖�Ă͂߂Ă݂Ă��A����͓K������͂����Ȃ�����A���Ӗ��ȍ�ƂƎv����B���̈ꎖ�i�������j���炾���ł��A�ɘ��̓���n�c�Â�����ł͂Ȃ��A�����ł����������Ƃ����������ł��낤�B�������A�u�R�����o���v�Ƃ܂ŏ����Ă���B����́A���̐Γ����A���̏�̎R�ۂɂ��������Ƃ��w���Ă���̂ł���B �Ƃ͂����Ă��A����͕ʒi�A���㉷���ے肵�Ă���̂ł͂Ȃ��B�ނ���ɘ��̓��́A�w���{���I�x�Ɓw�ɘ������y�L�x�ƎR���Ԑl�̉̂������A�����̓��㉷��̗����̂������őS����ɂȂ��Ă���Ƃ�������B�ے�Ȃǂ��Ȃ��Ăं��̂����ɒ��ׂ�Ε�����ł��낤�B ���㉷��̔������u�ɘ��̓��̍ċ��j�v�̒��ő�����̂��A�ɘ��̓��̌̎��E�`�����u���㉷��̑O�j�v�Ƃ��Čp������̂��̎��_�̈Ⴂ�͂��邪�A�z�q������āA���҂��ЂƂ̉�������ɂ��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B�����A�Ñ�́u�ɘ��̓��v�Ɠ��㉷������Ǝv������A�����Ə��R�����������肷��̂́A���j����点�錳�ł��낤�B����𐳂����F������A���ɔ[���ł��鎖���������Ƒ����͂��ł���B���܂ŕs���������������A�₪�Ė��炩�ɂȂ��Ă��邩������Ȃ��B���Ȃ��Ƃ��j�Ƃ́A�V��13�N���C�E��C���P��n�k�́u���ɘ�����v���s�o�v���A�ꎞ�I�Ȃ��̂ƈ��Ղɍl���āA�������Ă͂����Ȃ��B�����Ȃǂ͂��Ă��Ȃ��̂ł���B ���Ƃ��A�w���Q�ʉe�x�ł��A�ꕔ�͎��̂悤�ɏ��������ׂ��ł��낤�B ���� ����R�̘[�ɍ݂�A���Â͏n�c�ÐΓ��Ƃ��Ђ�����A���̍���肩����̉���Ɖ]�A�i�w���Q�ʉe�x�j�܂��w�ɗ\�Ð֎u�x�ɂ�����Ȉꕶ������B ����W�L����H�n�c�ÐΓ��A�c�c�����c�c�A���H�n�c���A�����}�K�̓����J�V�n�����n�����㉷��̐����ł͂��邪�A����͂܂����������̂��Ƃł͂Ȃ��̂��B�������猩�āA�������o����p�̒n�ɂ���n�c���J�i�Ƃ������j�̒n�Ƃ��ď̎^���Ă���̂�������Ȃ����A�����Ō����u�}�K�i�ӂ����j�v�Ƃ͉��ƂȂ��A���~�i�������j�E�K���̂��Ƃ̂悤�ɂ��v����B���̓��ɂ���̂Ȃ�A�����̓��V�J���낤�B�����ɓV�c�s�K�̎������������Ƃ����킯�ł���B�n�c�̍��́A�����̏n�c�Ái�̂��ɏn�c�Ɖ��߂�j�̂��Ƃł��낤�B����Ȃ�A���K�i���イ�����j���琼�ɂȂ�̂�����B�܂�́A������n�c�ÐΓ���ƍl����Ƃ��납��A�����Ƀu���������Ă����ł͂Ȃ��̂��낤���B �܂�A�����݂͂ȁA�Ñ�u�ɘ��̓��v���n�c�Â̐Γ��ł������Ƃ��납��A�m��Ȃ��ŁA���㉷������̂܂n�c�ÐΓ��Ɖ��߂��Ă��邾���Ȃ̂ł���A���̂Ȃǂ͉����Ȃ��̂ł���B ��ނȂ����R�� ��������ɂ́A���̂ق��ɂ��A�܂���ނȂ����R������B ���R�̓��㉷��͌Ñォ�猻�݂��ڂɌ�����`�Ō�����������Ă��邪�A�����̓��̉��́A�O�q�̂悤�ɌÑ�̂Q�x�̐k�Ђŕ��Ă���B���̌�A�n�c�Ñ����V���̍����Ŕ�Ђ��A�܂��c���̈ɘ��n�k�ɂ����ΐ�̖z���ɂ�������ĉ�ŁB�]�ˎ��ォ��͊��S�ȓc�n�ɕς��A���łɏn�c�̑����������Ă��܂��Ă��邩��ł���i��������̂̂Ƃ��A����Ă��̏n�c�𐼓c�Ə�\���ꂽ�Ƃ����B���݁A���c�͂���j�B�܂��A�V���̐w�Ȃǂ̑����ŎЎ��E���Ƃ��Ă���A�̖̂ʉe�����Ȃ�ꂽ���Ƃɂ���������邾�낤�B���̂��߁A���n�����Ă��A�N���C�����Ȃ��̂ł���B�n��̌Â�����̏Z����A���y�j�ƂȂǂ̈ꕔ�̐l�������A�����s���ł����قƂ�lj����m��Ȃ��̂�����ł��낤�B�ڂɌ����錴�^�炵�����̂������ȓ��V�J����ȊO�ɂȂ��̂ŁA���R�̂悤�ɐϋɓI�Ȃo�q���ł��Ȃ��̂�����A�����͂Ȃ��B �����A�S�������Ă悭���߂�ƁA�n�c�Â̐̂��M�킹��C�݂̒n�`��A�Γ��s�{�Ղ�`����Γ������{�E�k�V�{�_�ЂȂǂɎc��ËL�E�`���E���ՁE�_��������A�����\������A�B�V���̎R�R�ɂ���Ñ�̕����������͒f�w�Ղ�A�R��Ƃ�������A�����ɉc�Ƃ��铒�V�J����Ȃǂ��A���݂����̖��c�𗯂߂Ă���̂�����ɒm���Ă���̂ł���B����ɔޕ��ɖڂ����ƁA�����ɂ́u�����������v�Ɖr��ꂽ�ɘ��̍���̖k�ǂ��A���ȗ[�Ȃ̉_�ԂɋP���āA���͌��ƂȂ����Ñ�ɘ��̓��̉��̉h���̗��j���A�Â��Ɍ���葱���Ă���̂��F�߂���̂ł���B �u�ˋ���� ���ɗ������� �̎v�� 熎v�͂��� �ݓ��̏�́v���Ȃ��Ƃ��A�R���Ԑl�̎ˋ���̉��́A���̋k���̂��Ƃ������̂ł��낤�Ǝv���B
2009.09.28
�� �֘A�y�[�W �T�D�ѐϐ_�ЂƏ\��ʉ� �U�D�Ή��_�ЂƍՃP�� �V�D�n�c�Ì��z �X�D�k�V�{�_�ЂƏn�c�Ñ� 32�D�Ñ�u�ɘ��̓��v�i�Q�j 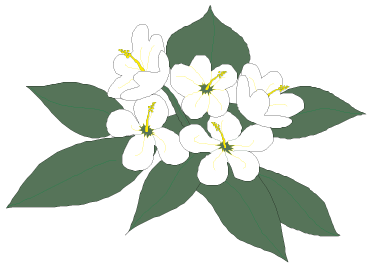 RELAX TIME RELAX TIME
|




![�ɑ]�T�_��](../image/s_history/s_history10/s_history10_5.jpg)



![���V�J���]](../image/s_history/s_history10/s_history10_9.jpg)


