INDEX
|
13.聖徳太子の周辺 (3) ~伊豫国湯の岡碑文について~ 碑文を読む 『伊豫国風土記』には、聖徳太子の湯の岡碑文というものが紹介されている。これは仙覚律師の『萬葉集註釈』と、卜部兼方の『釈日本紀』に引用されている逸文で、『萬葉集註釈』のほうには前文だけしか載せられていない。 先ず『萬葉集註釈』の前文から紹介してみよう。 「天皇等の湯に行幸すと降りまししこと、五度なり。」の3度目のところに、次のように書かれている。 上宮聖徳の皇を以ちて、一度と為す。及、侍は高麗の慧慈僧・葛城臣なり。時に、湯の岡の側らに碑文を立てき。其の碑文を立てし處を伊社邇波の岡と謂ふ。伊社邇波と名づくる由は、當土の諸人等、其の碑文を見まく欲ひて、いざない来けり。因りて伊社邇波の岡と謂ふ、本なり。記して云へらく、『萬葉集註釈』は、これで終わっている。 次に、重複箇所があるが、『釈日本紀』のほうになる。こちらは漢文なので、先に原文を記す。 以上宮聖德皇為一度。及侍高麗慧聡僧。葛城臣等也。于時立湯岡側碑文記云。 法興六年十月、歳在丙辰。我法王大王與、慧聡法師及葛城臣。逍遙夷與村。正觀神井。 歎世妙驗。欲敍意。聊作碑文一首。 惟夫日月照於上而不私。神井出於下無不給。萬所以機妙應。百姓所以潜扇。若乃照給無偏私。何異于壽国。隨華臺而開合。沐神井而◆疹。◆升于落花池而化溺。窺望山岳之■■。反冀子平之能往。椿樹相◇而穹窿。實相五百之張盖。臨朝啼鳥而戯吐下。何曉亂音之聒耳。丹花卷葉映照。王果彌葩以垂井。經過其下可優遊。豈悟浩灌霄庭意與。才拙實慚七歩。後定君子幸無蚩咲也。 上宮聖徳の皇を以ちて、一度と為す。及、侍は高麗の慧慈僧・葛城臣なり。時に、湯の岡の側らに碑文を立てき、記して云へらく。最初の前文は『伊豫国風土記』の編述者による説明文かと思われるが、『萬葉集註釈』では、高麗の僧は「慧慈」と書いてあり、また、『釈日本紀』では、「慧聡」となっている。しかしながら、どの史料を見ても慧聡(えそう)は百済の僧とあり、高句麗の僧は慧慈(えじ)なのであるから、この部分は、おそらく「慧慈」の誤写だと考えられよう。 次の碑文そのものは、『萬葉集註釈』には書かれていないので、『釈日本紀』に載る引用文に頼るだけになる。読み下し文ではすでに「慧慈」に修正されているが、原文はここでも「慧聡」と書かれている。比較するものがないから百パーセント誤りとも言えないが、かかりの文や、上宮皇子の師が高麗僧の慧慈であることなどを考慮すると、これもたぶん『釈日本紀』のほうの思い込みなどによる書き誤りかと思われる。 また、葛城臣は、用明天皇崩御後(587年)の物部守屋(もののべのもりや)らとの戦いで馬子・太子らの陣営にいた、葛城臣烏那羅(かずらきのおみおなら)のことではないかと想像される。 次に、「夷與(いよ)の村に逍遙(あそ)び、」とある「夷與の村」はおそらく伊豫の当て字であろうが、強いていえば、東予の村を指しているのかも知れない。これらの文は碑に刻まれた文字ではあろうが、当然ながら太子らの詩文ではなく、この碑文を記し、建立した者が書いた導入文だろう。 その次に来る本文は、自分なりの解釈による拙訳だが、以下のようになっている。 思うに、日や月は上空にあって惜しみなく照らし、神の井は地下から湧き出てあらゆるものに恵みを与えている。すべてはこの環境に応じてうまく運び、民らは安らかに暮らしている。もしこのように、照らし給えて偏(かたよ)ることがなければ、[恵みを受けた花はそれぞれの]うてなに従って自然に開き合い、[その様子は]寿国(じゅこく)とくらべても何ら異なるところがない。[里人が]この神の井に沐(もく)して疹(やまい)を癒すのは、[萎(しぼ)んで]弱った花が恵みの池に落ちて、再び生気を取り戻すようなものである。樹木の間から山崖を望み、自分を省みては、張子平(ちょうしへい)のように登っていけたらなあと思う。椿樹(つばき)は互いに重なり合って空の形になり、まるで[頭上に]無数の絹傘(きぬがさ)を張っているかと思うほどである。朝になると小鳥がやって来て戯れ鳴くが、そのにぎやかに囀りまわる声も、決してうるさくは感じない。紅い花は葉を巻いて日に照り映え、玉のような果実は花びらを覆って井に垂れている。その樹下を通りすぎながら、[自然を愛で、また詩文を考え]心ゆったりと遊びたいものだ。しかし、詩才には乏しくて、あの七歩の間にも詩が作れるという魏の曹植(そうしょく)のまねはとてもできないことを、まことに気恥ずかしく残念に感じている。[それだから]どうしてこの広大な自然の心など知ることができようか。後世に生まれる心賢い人よ、どうか軽くみて笑わないでほしい。もちろん、詩文だから個々の部分はいろいろに取れるので、異なった解釈をされる人もいるだろう。とくに「寿国」など、日本古典文学大系の注釈では「国を久しく栄えさせる」であり、「花が池に落ちて」も「花池(かち)に落ちて」である。 しかしこの碑文は、太子らが夷與の村で神の井を観て、その自然のしくみの不思議と奥深さとに感銘を受けて作ったものであること。何事も広く恵みを施して分け隔てのないことが、国政においても人びとに安心感を与え、万事が円滑に運んでいく基本であること。そして、このような環境のもとで心豊かに暮らしていくことに、その意義を置いているらしいこと。これらの点においては、大略、一致しているのではないかと思う。 椿樹(つばき)は春樹でなく、冬樹? ところで、この碑文を読むたびにいつも気になる点が一つある。 それは、ここに書かれた「椿樹(つばき)」や「丹花(にのはな)」は、たぶん、ヤブツバキのことかと想像するのだが、問題は、法王大王らが夷與の村を歩いて碑文を作ったとされる月が「十月」となっている点である。椿が咲く時期というのは、地方により早咲きの種類もあるだろうが、一般に開花の最盛期は1月から4月頃までの早春ではないだろうか。この「十月」が現在の11月か12月の初め頃に当たるとしても、この時季に、これほど盛んに椿が咲き誇っていたのであろうか。それなら、椿は春樹というよりも、冬樹といった方がいい。 「椿樹(つばき)は相◇(あひおほ)ひて穹窿(おほぞら)なし、實(まこと)に五百(いほ)つ蓋(きぬがさ)を張れるかと想ふ。このあたりまでは、受け取り方によっては、「十月」でも理解できない話ではない。しかし、 「丹(に)の花は葉を卷(あつ)めて映照(てりは)え、玉の菓(このみ)は葩(はなびら)を彌(おほ)ひて井に垂る。」ここまで来ると、「十月」だと今ひとつピンとこない感じがする。また花と実が同時に詠まれている点も、妙といえば妙である。熟成した実は9月頃には割れるというが、春の実がまだ割れずに、花を覆うほどにくっついていたのだろうか。それなら、現在とはずいぶん気候が違っていたとみえる。それとも、この神の井がもし温泉だったと仮定すれば、椿樹の周辺は地熱のためか、かなり温暖な環境になっていたのだろうか。 伊豫の湯と「湯郡」 この聖徳太子らの来訪の場所とされる古代の伊豫の湯は、『日本書紀』によると、天武天皇13年(684年)の白鳳大地震により壊没して温泉が止まっている。地元には湯の岡そのものが壊没したとの史料も存在することから、たとえ湧出がもどったとしても湯池の復元までは不可能で、684年以後の温泉の姿は大きく変貌していたと考えられる。そのためか、以後は天皇らの行幸も記録されていないのである。 ところが、713年以降に成立したとされる『伊豫国風土記』では、「湯郡」の温泉は往古のままの姿を保っているかのように書かれていて、これは、伊豫温泉最大の謎といえる。すなわち、この「湯郡」の温泉がのちの道後温泉を指すのだとすれば、道後温泉は、壊没した伊豫の湯ではなかったことになる。 しかもそこには、少彦名命(すくなひなのみこと)の伝説や、天皇らの行幸が歴史上、燦然と列挙されているわけで、その記事に従うなら、聖德太子らの夷與の村逍遙についても当然ながら壊没した伊豫の湯の出来事ではなく、この「湯郡」の温泉にあたる道後温泉のことになる。 とはいえ、他方では、道後温泉そのものが依然として古代の伊豫の湯であるかのように取り扱われている矛盾した現実もある。それは、M8以上の大震にもかかわらず、古代の伊豫の湯は一時的に湯の供給を停止しただけで、すぐに復旧しているはずとの無意識の判断が働いているためで、そのため、この伊豫の湯こそが間違いなく現在の道後温泉だと最初から思い込んでいるからであろう。しかし、上記の事実に従えば、伊豫の湯は道後温泉ではないはずである。 ただ、問題は、この「湯郡」の2字にある。誰が、いつ、なぜ「湯郡」と書いたのか。たしかに、飛鳥の木簡には「湯評」の文字が出ている。また、『法隆寺縁起并流記資材帳』には、747年に温泉郡の文字がある。従って、その間をつなぐ郡名として「湯郡」の名称は大いに考えられよう。しかし地元には、道後温泉は746年の開発との史料もあることから、『伊豫国風土記』の成立年代については慎重を期す必要があり、この「湯郡」の温泉がほんとうに温泉郡のことなのかは、今以て不明である。 ひとつには、ここでいう「湯郡」は必ずしも温泉郡の意味とは限らず、「(伊豫の湯)の郡」の略称とも考えられなくはない。古代の「伊豫の湯」が存在した里の意味になる。ほかにも、『伊豫国風土記』に載る「湯郡」の諸伝承や、山部赤人の歌が、すべて同じ場所を指しているのかどうかについても、よく検討しなければならないだろう。 伊豫の湯と西条の関係 それはさておき、西条には昔から熟田津(にきたつ)の伝承地があり、斉明天皇逗留に関わる二つの神社や口伝があって、3体の祭神像(中央が白衣の天子像と1体は春宮と伝える)と32体の随臣の木像が遺されていて、その1体の内部には「熟田津村橘」の墨書が認められている。そして、神社によると、この随臣像のうちの1体が、社家の高橋家の遠祖だとも伝えている。 また、昔の海岸線から1キロほど南の山麓には温泉宿が存在する。湯之谷温泉である。今は冷泉を沸かしているが、社家の口伝によると、この地にはかつて岡があり、石湯の岡(いわゆのおか)と称していたそうである。また、月見の岡、三日月の岡との言い伝えも残されているらしい。 加えて、西条からは松山よりもずっと間近に、伊豫の高嶺と呼ばれる石鎚山の北壁を仰ぎ見ることが出来る。さらに往古の熟田津の地には現在でも安知生(「あんじゅう」安らかに生まれるを知るとの意か)の古地名があり、これに関して、その地の石湯八幡宮の古記は、大伯皇女(おおくのひめみこ)誕生の逸話を伝えている。また、熟田津はのちに熟田と改名されたが、天文・慶長の地震と、高潮と洪水で村そのものが壊滅した。跡地は水田となったため、江戸時代に誤って「熟田」が「西田」と、一柳西條藩に上申されたといわれ、西田は現在あるが、それ以後、熟田の地名は西条から消えてしまったのである。 山部赤人の万葉歌には、本歌に対して、 ももしきの大宮人の飽田津に船乗しけむ年の知らなくの反歌が添えられている。 この「飽田津」は、熟田津の字に「饒田津」の字が当てられていたものを、筆文字のため読み誤ったものと考えられ、本来は熟田津のことであろう。いくら書いてあっても、「あきたつ」などと読むべきではないと思うが、この歌の本歌には、伊豫の高嶺と射狭庭の岡と、行幸處としての「み湯」が詠み込まれているのであり、この両歌には密接な関連性があるものと考えるのが自然であろう。つまり、ほとんど同じ場所だということになる。 これらのことから、この赤人の射狭庭(いさにわ)の岡とまったく同所かどうかは別として、法王大王の湯の岡碑文及び伊社邇波(いさには)の岡に関しても、同じ地域ではないかと考えられるだろう。 たしかに、江戸時代あたりの史料には、松山の道後温泉も西条と同じように、古くは熟田津石湯と称したように書かれているものが何冊かある。しかしこれは、古代伊豫の湯を後世に道後温泉と勘違いしているところから、西条の熟田津石湯を単に擬したものと思われ、意図して書いたものではない代わりに、根拠や実体もない名前だけの伝承ではないかと考えられるのである。松山には、熟田津石湯を実証する具体的な伝承物はこれといってなさそうだし、伊社邇波神社なども後世の神社であり、証拠とはならない。道後温泉もたしかに古い温泉だが、現存するだけで古代の「伊豫の湯」だと断ずるのは短絡的に過ぎよう。 西条とは一見、関係なさそうに思われる聖徳太子。その存在に少しずつ興味が湧いてきたのも、一つには、こうした理由があったからである。 2010.02.20
◆ 関連ページ 11.聖徳太子の周辺 (1) 12.聖徳太子の周辺 (2) 7.熟田津幻想 10.古代「伊豫の湯」と湯之谷 ■ 基礎資料・参考文献等 『萬葉集註釈』 『釈日本紀』 『風土記』 日本古典文学大系 岩波書店 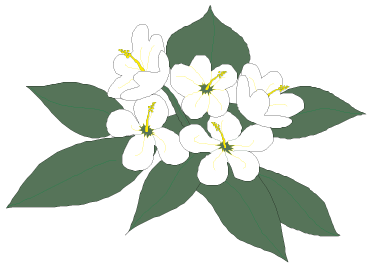 RELAX TIME RELAX TIME
|