INDEX
|
12.聖徳太子の周辺 (2) ~『隋書』倭国伝について~ 隋書倭国伝の内容 正しくは『隋書・列伝・東夷伝・倭国』となっているが、この倭国伝の記事内容についても、いろいろと論議されていることは知っている。といっても、論議の内容についてはそれほど関心がないから、詳細までは分からない。しかし私自身は、これを読んでみても何の矛盾も感じないのである。そこでこちらについても、自分なりの解釈を簡単に付け加えてみたい。 ただし、倭国伝の内容を全部は書けないから、とくに論議されているとおぼしき箇所を拾って書いてみる。 『隋書』倭国伝の内容は、3度の使節の記事に分割できるが、その前に倭国の位置・地勢、倭国へ至る順路、倭国の気候・暮らし・習慣、中国との関係、邪馬台国の卑弥呼などに関して次のような説明が付されている。 イ妥國 〔注1〕 在百濟、新羅東南、水陸三千里、於大海之中依山島而居、……これらに始まる倭国の情報は、隋代に見たものでも聞いたものでもなく、すべて過去の史料から取り込んだ情報である。 倭国とイ妥国 ここに「イ妥国」とあるが、これが「倭国」の誤字であるかないかは編述者でないと分からないから、倭国とイ妥国については、次の二案を上げておきたい。 [誤字である場合] 史書の編纂時に「倭国」を写し誤ったのではないかと思われる。日本に「イ妥」などという国はない。 『隋書』を参考にした『北史』にもこの字が用いられているが、『北史』では「倭国」の表記も混在している。また、『太平御覧』にも「『後漢書』に曰く」として、「イ妥国」と書かれているが、その出典としている『後漢書』は「倭国」となっている。隋書の見た『後漢書』と『太平御覧』の見た『後漢書』が、同一資料だったのではないだろうか。 書司は元より、編者もすべてに精通しているわけではないから、とくに筆書きの場合など、地名や人名などは誤写しやすいのである。国の内外を問わず、例はいくらでもあり、一字をこうだと思えば、すべてを誤る。 たとえば、「邪馬壹国」も、正しくは「邪馬臺国」であろう。卑弥呼の後継者である宗女「臺與」に対しても「壹」の字を当てているが、壱岐に対しては「一」の字を使っている(おまけに支の字を大と誤写しているらしい)から 、本来「臺(たい)」であったことがすぐに分かるのである。この場合の「たい」は、倭語で言えば「と」に当たる。「と」 と言ったのが、向こうでは「たい」に聞こえただけであろう。 [誤字でない場合] 「倭人」は元来「倭」の一字だけで「わじん」を表現していた。最初、彼らは自分たちのことを「わ(我)」とか「あ(吾)」とか言っていたが、漢人から見ると小柄で従順な人々だったので、「人偏」に「委ねる」を以て「わ」の字に当てたのである。 また、性格的に穏やかで争いを好まなかったこともあり、「人偏」に妥協の「妥」の字を以て「あ」の字に当てることもあっただろう。「妥」は「安」の字に通じ、「安」から平仮名の「あ」の字も出来ているのである。したがって、「倭」は「わ」、「イ妥」は「あ」を表し、普通は「倭国(わこく)」と書き、また時には「イ妥国(あこく)」と書いたりしたのだと思う。 たしかに、これらを、元の字義から「イ」と発音したり、「タ、タイ」と読んだりすることは文字としては可能だが、元来が「わじん」を指す言葉なので、そのような読みは全く無意味にして不必要といえよう。「イ」などと発音したら本来の意味を損ない、「タイ」などと読めば、「イ妥国」は「弱国」の意味になる。煬帝が怒って「弱国」の意味で使用させたのではないかという人もいるが、「イ妥国」の文字は『隋書』倭国伝だけに限られているのではない。『北史』はともかく、『太平御覧』にも使用されている。しかも、「『後漢書』に曰く」となっているのだから、その解釈は当たらない。おそらく『太平御覧』の見た『後漢書』と、『隋書』の見た『後漢書』とが、同一資料だったのだろう。 このように『隋書』東夷伝ほか2,3の書では「イ妥(あ)」字のほうを用いているが、意味するところは「倭(わ)」字と同じことである。『隋書』でも「帝記」のほうには倭国と書かれているのであるから、「東夷伝」でも「倭国」のことで間違いない。 最初の遣使 その倭国について概説した後に、最初の遣使の記事に入ってくるが、開皇二十年(推古8年、600年)としてあり、隋は高祖文帝の時代である。そのため、この箇所の記事については、2度目以降の煬帝への使節の記事とはまた別資料に依拠したものではないかというふうにも考えられよう。内容も、そのほとんどが伝聞による倭国の情況説明に終始し、2度目以降のような、使節による実際の行動を通していない。 たしかに、冠位十二階の制から始まる推古朝の記事も多く見かけるが、過去の史料からとおぼしき情報も各所に使われており、その上に唐代の知見まで加味されているようである。阿蘇山にしても、如意寶珠にしても、見たものか聞いたものか、過去や唐代の見聞なのかもよく分からない。鯨面文身(げいめんぶんしん)やクガタチなどの風習が、推古天皇の時代にも、まだ残っていたのか。火(火の字を犬とまちがった?)をまたぐ話などは、弥生時代の竪穴式のものではないのか。おそらくは、遣使の話や、前王朝の史料に拠るものであろう。 この最初の遣使にしても、たぶん、百済とか高句麗の使節に随伴して案内してもらったものであり、倭国から渡海したものか、半島に駐在していた使者なのかも不明だが、はじめてなので、隋の様子を見に行った程度のものではあるまいか。方物は用意していたようだが、国書も何も持参していない。礼儀をわきまえず、尊大で、自国のことを問われても「天を以て兄とし、日を以て弟とする」などと、いい加減なことしか答えない。高祖も気分を害したのか、「義理なし」と諭している。本式の遣隋使というようなものではなかったのであろう。そのため『日本書紀』にも書かれていないのである。一方で、百済国などは隋の当初から朝貢を続けていたのであり、煬帝の帝記にも、 大業四年三月 壬戌 百濟・倭・赤土・迦羅舍國並遣使貢方物 〔注2〕とあるように、倭国だけが朝貢していたのではないのである。むしろ、倭国は遅れていた。 倭国の情報 このような情況だから、隋としても使者から聞いた話だけでは、倭国の情報などは概略しか掴めず、欠落した箇所は過去の史料により補完するしかなかったであろう。こうした別資料であったものを、唐の時代に使節裴世清一行による資料を加えて、倭国伝という一条に編纂したのではないかと思うのである。 そのため、この開皇20年の記事の中には、隋以前の史料や以後の資料も部分的に混在しているかもしれないという認識が、解読に当たっては先ず必要とされるだろう。冠位十二階の施行にしても、『日本書紀』では開皇20年よりは後年のことであり、そうした認識に立たなければ、これらの記事は解釈できない。なぜなら、『隋書』は唐の時代に勅撰されたが、その際、南北朝の歴史も同時に編纂されているのである。また、『後漢書』や『魏志』などの過去の正史も多数、参考にされているはずであり、それらの資料が、ここに部分的に使用されている可能性については否定できないだろう。 見たところ、 開皇二十年、イ妥王姓阿毎、字多利思北孤、號阿輩[奚隹]彌、……。この辺りには、例えば雄略天皇の資料が一部使用、又は混在しているのではあるまいか。つまり、隋の前王朝である南北朝の倭王武の資料である。そう考えると、この記事は何の違和感もなく理解できてくる。 「あまたらしひこおおきみ」は代々の天皇の一般称として何ら問題はない。「多利思北孤」を「多利思比孤」と訂正したものもあるが、どちらにしても同じことである。「ホコ」であれ「ヒコ」であれ、「垂(足、帯)日子」を相手がそう聞き取っただけのことであり、「あまたらしひこ」は天孫のことである。字名にすぎない多利思北孤なる人物がほかにいるわけではない。いるとしたら、雄略天皇のことであろう。 「王妻號[奚隹]彌(ヒメ)、後宮有女六七百人」と書いているのも、推古天皇の時代とすれば、いささか疑問を感じる。たしかに、采女(うねめ)などはかなりいたと思うが、そんなに仕えていただろうか。しかし、勇武に長けてカリスマ的な雄略天皇の時代ならば、ある程度の理解はできそうである。 次に、「名太子爲利歌彌多弗利」とあるが、これは「太子の名はシラカミオウジ」と読むのではないかと思う。「リカミタフリ」などではないだろう。「爲」は前の文脈からみて「なす」ではないと思う。「シ(ィ)」である。「利」は「たらしひこ」の「ラ」で、前半は「シラカミ」。「多弗利」は「タフリ」ではない、「オフジ」である。「ジ」を、「リ」と聞き取っただけであろう。「太子の名はシラカミオウジ」と書いているのであり、白髪皇子は雄略天皇の皇太子で、清寧天皇のことではないだろうか。 たしかに、聖徳太子の御子にも似たような王(白髪部王、山背大兄王…白髪が多いが後年のこと)がいるが、聖徳太子とその子を外交上で大王・太子と並べるのはいかがかと思うし、聖徳太子に官女が六七百人もいたのか。また、聖徳太子が27歳ぐらいの時だから、御子はまだ若齢のはずである 〔注3〕 。このように中国の史書でも、異国の情報となると曖昧な点も多いのであり、あまりきまじめに受け取るのも考えものであろう。 一百二十人の軍尼有り。猶お中國の牧宰のごとし。八十戸に一伊尼翼を置く。今の里長の如く也。十伊尼翼は一軍尼に屬す。とある。軍尼は「くに」「ぐんじ」「(こ)くじ」「(す)くね」などと読むのか。「くに」と読んで国造のことかとする人もいるが、国造なら戸数が全然合わない。伊尼翼(稲置)はあっただろうから、いずれにしても、稲置の上の長である。合計9万6千戸(「戸は十万ばかり」と書いている)になるので、倭(やまと)の戸数ではないだろうか。邪馬台国の時代には7万余戸としていた。 隋に至り、其の王、始めて冠を制す。錦綵(きんさい)を以って之を爲し、金銀を以って花を鏤(ちりば)め飾りと爲す。最初の物見がてらの使者がバカにされて懲りたのか、裴世清が来たときには、皇子・諸王・諸臣らがこのような冠で迎えたことが、『日本書紀』にも書かれている。とすれば、物見も無駄ではなかったということであろう。 文字は無く、唯だ木を刻み繩を結える。佛法を敬い、百濟に佛經を求め得て、始めて文字有り。この辺りは、『日本書紀』と比べても、ほとんど異なるところがない。 遣隋使小野妹子と隋の使節団 2度目は大業三年(607年)であるから、これからは煬帝(ようてい、ようだい)の時代になる。 其王多利思北孤遣使朝貢。使者曰:「聞海西菩薩天子重興佛法、故遣朝拜。兼沙門數十人來學佛法。」其國書曰「日出處天子致書日没處天子無恙」云云。とあり、有名な文章である。ここに「其王多利思北孤」をまた出しているのは、おそらく、前の文書を受けたのだろう。王名が分からないのだから、字名の「多利思北孤」と書くしか方法がないのである。おそらく、開皇20年の文書が別資料だったために、「其王多利思北孤」をここに置くことで、文章をつなぎ、一貫させているのではないかと思われる。そうでないなら、「大業三年、また遣使朝貢」でもいいはずである。当然、ここでいう使いとは、大礼小野妹子のことであろう。一応、敬意も表しているが、前回の遣使がバカにされただけに、多少、高飛車な感じの国書である。 その明年(608年)、帰国の小野妹子に伴い、裴世清(はいせいせい)ほか12名が倭国への使節として旅立った。「裴世」と書いているのは、唐の皇帝の諱を避けたものらしい。秦王國を通って、たぶん、宇佐から国東方面へ向かっているから、阿蘇へは行っていないはずである。その秦王國から後「十餘國を經て、海岸に達す」と書いているので、最後は海へ出たわけで、当時は、博多湾や遠賀川河口のほかにも、姫島辺りからの瀬戸内海航路があったものと思われる 〔注4〕 。倭(やまと)王権は代々、中国を警戒していたと見えて、畿内への道順については必ずしも精確に教えていないようだ。あえて回り道をしたり、京(みやこ)の方角を惑わしたりする。九州から後は航路で行くから、外国の使節には分かりにくいのである。とにかく、難波津に到着した。 倭王と裴世清の接見 このあたりからは『日本書紀』にも、使節出迎えの様子がかなり詳細に記されている。筑紫から難波津まで案内したのは『日本書紀』によると、難波吉士雄成(なにわのきしおなり)であった。難波津に出迎えて使節を接待したのは、『隋書』では「小德阿輩臺」とあるが、これは大河内直糠手(おうしこうちのあたいあらて)で、「後十日、又遣大禮哥多毘」とあるのは、額田部連比羅夫(ぬかたべのむらじひらぶ)のことではないかと思われる。その後、8月3日に海石榴市(つばきち)に出迎えてから、飛鳥の京に入った。 ここで天皇と裴世清が接見。使節は挨拶を言上して『日本書紀』では皇帝からの親書を渡し、天皇はこれらにおおいに喜んで、 「我、海西に禮義之國大隋有りと聞く。故に遣わして朝貢す。我は夷人にして海隅に僻在し、禮義を聞かず。是を以って境内に稽留し、即ち相見せず。今故に道を清め館を飾り、以て大使を待つ。冀は大國惟新の化を聞かん。」このように裴世清に言ったと、『隋書』では書かれている。隋が一応、礼儀にしたがって誠意を見せたので、今度は多少わだかまりも解けて、へりくだったのである。 しかし、双方にそのような若干の交歓があったとしても、両者の間には臣と連が控えていて、親書や言葉をいちいち移動して取り次いでいるのだから、その間隔はかなりの距離があったと考えられる。御簾(みす)まで用意されていたかどうか分からないが、天子の装いで冠を付けておれば、屋内なら暗いし、ジロジロ見るわけでもないので、男だか女だか分かるものではない。推古天皇であったという保証はないが、私は、女帝であることは最初から最後まで相手に言わなかったと思う。箝口令(かんこうれい)まで布いたかどうかは分からないにしても、積極的には言わなかった。なぜなら、国書に「日出ずる處の天子、書を日没する處の天子に致す。無恙きや」と言っているように、仏法世界で隋と対等の友国関係を求めていた太子だったから、倭国の天子が女帝だと分かれば軽く見られて、以前の冊封関係に戻されることを元より懸念していたであろうと思う。それに、外交・内政と、じっさいに政務に当たっていたのは皇太子だったのである。倭王については、最初から最後まで名前すら知らなかった 〔注5〕 からこそ、『隋書』には書かれていないのであろう。 3度目の使節 後日、天皇は返書を届け、小野妹子と通訳を付けて、使節を送り返した。これが、『隋書』では3度目の使節に当たるのである。そして最後に、「この後、使節の往来は絶えた」として、この条を結んでいる。 しかし、その間にも一度、朝貢があったという人もあり、その後の推古22年(大業10年、614年、)にも犬上君御田鍬・矢田部造を遣わしたことが『日本書紀』に書かれている。この頃は、隋もすでに混乱期に入っていただろう。 いずれにしても『隋書』に書かれた遣使は前記の3度だけであり、しかも最初の遣使は、正式の使節であったのかどうかも疑わしい 〔注5〕 。結局、『日本書紀』にもあるように、大礼小野妹子を遣わしているのは、この2度にわたる遣隋使だけのようだ。その後、高句麗との戦闘で国力を衰退させた隋王朝は618年(推古26年)に禅譲(ぜんじょう)して滅び、唐が支配したのである。 2010.02.10
〔注1〕 イ妥国の「イ妥」の字は画面に表示されないため便宜上「妥」で代用しているが、実際には旁(つくり)の上部が末広がりになっている。 〔注2〕 この大業4年3月の倭の遣使も小野妹子だと思われる。『日本書紀』では推古15年(大業3年)秋7月3日に出発して、明くる16年(大業4年)夏4月に帰国となっているので、まだ滞在中だったのだろう。『隋書』琉球国にもそれらしい記事がある。もしくは、「帝記」のほうが全体的に1年遅れになっていることも考えられる。大業6年1月の遣使についても同じで小野妹子(蘇因高。小が蘇で、妹子が因高)の1年遅れだと思う。大業4年~5年の小野妹子の朝貢記録が見当たらない。 〔注3〕 『新唐書』に「用明、亦た目多利思比孤とも曰い、隋の開皇末に直(あた)る。始めて中國に通ず」、また『宋史』に「自多利思比孤」とし、用明天皇に続いて聖徳太子が紹介されていることから、この二人のことを書いているとも受け取れなくはない。 ただし、『新唐書』や『宋史』の記述が隋代の資料に基づくものかどうかは明確でない。後に日本から得た天皇の情報や遣唐使などの話を参考に、開皇年と太子の父子関係から用明天皇と判断していることも考えられ、天皇の年代や在位が『日本書紀』の内容とは一致しないなど不審な点も多い。 また、「目多利思比孤」については「アメタラシヒコ」の「ア」が取れたのか、逆に「メ」が頭にくっついたのか、それとも「ヒタリシヒコ」の誤りなのか、「自多利思比孤」については「自らタリシヒコ(と表す)」の意味なのかどうか分からないが、『隋書』本文には「目(自)多利思比孤」なる文字はひとつも存在していない。たとえば、後代の史書が「豊日尊」から判断して「日多利思比孤」と書いたが、途中で「目多利思比孤」に誤写され、さらに「自多利思比孤」に転化してしまったようなケースも考えられるだろう。 したがって、こうした後代の史書はひとまず置くとして、『隋書』では裴世清一行の来日後でもなお倭王の諱(いみな)は書かれていないのだから、王・妻・太子らに関しては、歴代倭王の通例に従って紹介しているだけなのか、もしくは、当時の倭王が誰なのかをまったく認知していなかったとしか考えようがない。「其王多利思北孤」の語句から推測すると、むしろ知らなかった可能性のほうが大といえるだろう。『隋書』における倭王の情報がこのように不確実な内容に終始しているのは、当時の倭国が、女帝であることを秘して、相手方に知らせなかったからではないかと推測されるのである。 ただし一説にあるように、この記事中の「利歌彌多弗利」が、間違いなく「和歌彌多弗利」の誤記であると断言できるのなら、これは太子の個人名ではなく、日継御子(ひつぎのみこ)などの意味になるのかもしれないが。ただその場合は、この「阿輩[奚隹]彌(おおきみ)」も特定の大王を指すのではないことになる。また「和歌彌多弗利」なら「名」ではなく「號」とかになるのではないか。 〔注4〕 「秦王國から後、十餘國を經て、海岸に達す」を、陸路から海岸へ到達したと解釈した場合、九州では「十餘國を經て」の説明に齟齬(そご)が生じるので、実際には九州の秦王國を過ぎ、船に乗って瀬戸内海の海路を経てから海岸に到達したとの意味なのかもしれない。秦王國から後、海路で山陽道・南海道の国々十余国を経て難波津に到着したと解した方が、たぶん正しいであろう。次の「竹斯国より以東、皆倭に附庸す」の文章とも符合する。『日本書紀』にも「難波津に泊まる」とあり、これは船が泊まることであり、飾り船で出迎えている。舒明4年の唐使「高表仁」も海路を取り、遣唐使などもみな船で筑紫へ向かっているので、隋の使節だけがわざわざ山陽道の陸路をとる理由は考えにくい。 〔注5〕 『隋書』の時代には天皇の漢風諡号がなく、大業3年でも字(あざな)の多利思北孤と記されていることから、裴世清来日後も王名については、やはり知らなかったのではないかと思う。他方、雄略天皇については、稲荷山古墳鉄剣銘や江田船山古墳太刀銘に「獲可多支鹵大王」とあり、「大王(おおきみ)」の称号が使われている。 〔注6〕 『宋史』には「隋の開皇中に使いを遣わして法華経を求めさせた」と記されていて(後に日本側からもたらされた情報かもしれないが)、これが最初の遣使の主目的だったとすると、聖徳太子が仏典を求めて私的に遣わした使者の可能性が高くなるだろう(「法華義疏」)。 ◆ 関連ページ 11.聖徳太子の周辺 (1) 13.聖徳太子の周辺 (3) ■ 基礎資料・参考文献等 図書 「倭国伝」関係資料 『邪馬台国辞典』武光誠 同成社 1986 「魏志」東夷伝倭人条 「歴史群像」学習研究社 1989 『日本書紀』 『日本書紀』 宇治谷孟訳 講談社学術文庫 『続日本紀』 宇治谷孟訳 講談社学術文庫 『倭国伝』 藤堂明保・竹田晃・影山輝国訳注 講談社学術文庫 ウェブ・サイト ALEXの書斎 漢籍の書棚 http://www.ceres.dti.ne.jp/~alex-x/kanseki/menu01.html#MOKJI 古代史獺祭 http://www001.upp.so-net.ne.jp/dassai/sitemap/sitemap.htm (『隋書』の読み下し文については、「古代史獺祭」さんから多く参照させていただきました。) 以上、お礼申し上げます 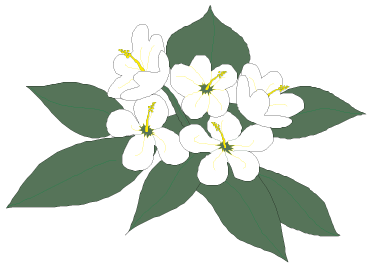 RELAX TIME RELAX TIME
|