INDEX
|
21.高峠城推論 高峠城の沿革 高峠城(たかとうげじょう)は西条市州之内(すのうち)の高峠山に築かれていた戦国時代の山城で、元々は高外木城(たかとぎじょう)と称した。新居・宇摩二郡の主城で、地元の伝承によると、その築城の歴史はずいぶん古いとされている。 『予章記』によると、聖武天皇の天平12年(740年)に筑紫の太宰府で藤原広嗣の乱が起こり、南海道の越智玉澄(おちたまずみ)らも朝廷の命を受けて鎮圧に向かった。しかし、その道中のちょっとした出来事が原因で玉興(たまおき)・玉澄親子(兄弟だが、養子)の間に不和が生じた。そのため、
玉興は新居郷に居住し玉ふ。故に後は新居の一族と称す (『予章記』上蔵院本)とある。新居郡(にいぐん)に居住したのが玉興だか、玉澄だか分からないが、不和なのはこの二人ではなく、玉興と玉澄の兄なので、長福寺本をよく読めば家兄の玉守(たまもり)のことらしい。地元の伝承でも兄の玉守(前名玉男)だとされている。そして、この越智玉守が居住したのが、高峠城の始まりだとしているのである。 上蔵院本には、そのころ橘正清(長福寺本は清正)という人が国司であったので、これと契約して「姓をも橘と改む」となっている。つまり、橘の姓をもらったか、養子になったということらしい。しかし、それなら玉守の子孫は当初から橘姓でなければならないが、実際に橘姓を名乗ったのは玉守の5代孫の橘実遠の時からだとされていて、当時の伊予国司の中には「橘正清」なる人名も見当たらない。 また、越智玉守は伊予橘氏の祖とはされているが、新居氏の祖ではなく、新居氏の祖は、越智系図をたどると玉澄にある。しかしこの玉澄も、宇摩・越智・風早の3郡には居住したであろうが、新居郡に常住したかどうかは史料がなく、玉興にしても同様である。ただ、玉澄の長子益男の子実勝が西條御館と書かれていることから、もし玉澄との関連性を考えるなら、そのあたりになるのではないだろうか。 一方で、新居の浦にも別の館があって、玉守はここに居住していたとの話も聞いたことがある。上記の上蔵院本においても、「新居郡」でなく「新居郷」となっている。たしかに当時、新居郡はまだ神野郡(かんののこおり)と呼ばれていた時代であるから、そのころから新居殿(にいどの)と称されたのなら、玉守の居館は郡下でも新居郷に求めるほうが理には適っているだろう。もちろん、それが事実だとしても、おそらく郷名から新居殿と称されただけのことで、高峠の主、新居殿とはまた別の話ではないかと思われる。
新居浜市一宮町にある一宮神社(いっくじんじゃ)の由緒には、玉守が一宮神社をとくに信奉したことが伝えられていて、一宮神社は越智氏の奉祭する大山積神(おおやまづみのかみ)ほかを祀っている。境内に建つ昭和の石碑には和銅2年の勧請と記してあるが、神社略誌によると、これは雷神と高おかみ神を大三島から奉遷した年にあたり、大山積神は往古からとの由である。最初の社殿は小千益躬(おちますみ)の創建によると伝えている。 この一宮神社の社家は矢野家で、矢野実遠の第二子千寿丸が『日本霊異記』並びに『文德天皇実録』の上仙菩薩(寂仙菩薩)である旨の碑文と、社家の出である上仙(じょうせん)の大きな自然石の奥津城が、矢野家の墓所に建てられている。 上仙の父親とされる矢野実遠は、上仙の没年から指折ると、越智玉守とほぼ同年代の人になるようだ。また、上仙菩薩自身が、越智氏また秦氏の出とも伝えられている。 この辺の事情については、『姓氏家系大辞典』にも次の関連史料が見受けられる。 また一宮社記、矢野系図等に、玉守の裔實遠の事を載せて、「玉守-益興-益連-實連-實遠(是の時、勅により、神野郡を改めて、新居郡と為す。之により實遠の家名を改めて新居殿と稱する也。これによると、玉守の子孫を新居殿と称したのは新居郡からであり、橘姓に改めたのも、実は玉守ではなく、橘実遠の時代となっている。この時期に嵯峨天皇から神額を献じられたことは事実のようで、現在も一宮神社に社宝として保存されている。 したがって、このように新居浜の一宮神社との所縁(ゆかり)が深そうな越智玉守が、西条市州之内の高峠に居住したのかどうかについては、今のところ分明でない。 一つだけヒントとして考えられることは、この新居殿なる越智玉守と、新居殿なる高峠の主が、橘実遠を通して後世に結びつけられたのではないかということである。なぜなら、新居氏は越智氏との関係以上に、高峠近くの伊曽乃神社別君・氏子との関わりが深いと推察されるが、この高峠のある州之内近郷の地名を古来「橘の里」と称しているからである。赤間ノ関における平家方の遠矢の名手「新居ノ橘四郎」にしても『予章記(長福寺本)』では伊予橘氏の後裔として記されていて、正解かも知れないが、解釈によっては「新居橘ノ四郎」とも受け取れて、この橘の里に由来しているのかもしれず、その場合、橘は元より地名であって、正清(清正)にもらった氏としての橘姓とは明らかに異なっている。 長福寺本にも、 明神も河野の朝日弥高、新居の夕日弥低と仰けるを恨申て、…中略…姓をさえ橘と改らる。とあって、もう越智姓も名乗らない、三嶋の神も奉斎しないように書いているが、玉守や子孫は一宮神社を尊崇している。また社記によると、玉守は橘姓を名乗っていない。つまり、「新居」といっても、これは玉守やその子孫のことではなく、橘の里の高峠・新居氏のことを指しているようにも理解され、玉守の伊予橘氏と、伊曽乃神社・玉澄系統の新居氏とが、伝承の中で渾然一体化してしまっていることも疑われるようである。 南北朝時代の高峠城 その次の史料は、南北朝時代応安2年(1369年)に讃岐から新居・宇摩に進入した細川軍に対して、河野通直(通堯)が、この高峠城に立てこもって防戦したことが記されている(『予章記』ほか)。従って、当時は河野氏の領分であったのかもしれない。越智玉守から河野通直まで、多少の伝承はあるが、奈良時代から600年以上、史料が全く飛んでいる。その10年後には壬生川の佐志久原(さしくばら)で通直が戦死し、新居・宇摩の二郡も再び細川氏に奪われてしまったようである。 しかし、その直後の1381年には、将軍足利義満の仲裁で河野と細川の和睦がなり、通直の嫡男河野通能(みちよし、亀王丸、通義)に伊予一国の守護職が安堵される。ただし、新居・宇摩の二郡は細川の知行とし、二男通之(みちゆき)が細川頼之の養子となったが、そのことに関して、保國寺文書の次の書状が問題視される。 細川満之書状保國寺(ほうこくじ)は西条市中野の伊曽乃神社隣りにある禅宗の名刹で、室町時代の石庭でもよく知られており、この保國寺と高峠城は距離的にも近い。
書状の康応元年は1389年で、満之は細川満之に当たるが、問題とは、宛名に書かれている石川入道なる人物が誰かという点にある。というのも、この石川入道について『保國寺縁起』(『萬年山保國禅寺歴代略記』享保16年[1731年] 53世住職 九峰禮渕著)が、これは、石川六郎入道通之(河野通之)のことだと述べているからである。 理由についてはいろいろ書かれているが、たとえば、石川の姓は河野を改め、細川の川の字と、頼之の之の字を充て、石川通之と変えた。また入道については、和議による契約とはいえ親二代の怨敵の養子とされたことは不忠・不孝を生きることになる。したがって、仏門に入ったのだとしている。 ただ、肝心の石川の石の字についての説明は何もなされていない。また満之の書状の年でも六郎通之は18歳であり、いくら不忠・不孝のためとはいえ、入道を名乗るのはまだ若すぎはしないかとか、石川の次に六郎の名が記されていないが…等々の基本的な疑問についても何も触れられていない。が、とにかく、九郎通能(通義)は道後を領して湯月城に居し、六郎通之は道前を領して高外木城に居した。そして、この石川六郎通之入道こそがほかならぬ石川氏の元祖であり、二代目がその子の信濃守通信である。かくして、石川氏は代々河野通之の子孫であるから、『澄水記(ちょうすいき)』にいう備中石川氏よりの城主招請譚などは悲しむべき妄説であると一蹴している。 高峠城主は誰? しかし、河野通之の子息に信濃守通信がいたのかどうか知らないが、河野氏系譜によると、河野通元(みちもと)が六郎通之の後継者となっている。従って、細川勝久が送った書状に信濃守通信の名が見られるだけで、単にそれを理由として、このような推論が成立するのかどうかは疑問がある。 ただ、『保國寺縁起』はこれらの論拠を『左海予章記』というものに依拠しているようだ。『小松邑志』にその『左海予章記』が引用されている。 左海予章記に、細川頼之河野と和平の後、河野通之石川六郎と名乗り、高外木に住し、道前を領す。舎兄通義逝去の後河野に復し、後又石川を名乗る。通之の一子を石川信濃守通信と云、是石川の二代なりと。『伊豫温故録』もこれと同説を採っているが、『伊豫温故録』は『保國寺縁起』を見て書いているから仕方がない。しかし、『小松邑志』は「この説は恐は非ならん」と否定している。 では、この説にもし誤りがあるとすれば、『左海予章記』はなぜそんな誤りを犯したのか。はっきりはしないが、強いて推測されるとすれば、次の理由なのではあるまいか。
『小松邑志』では前述の『左海予章記』の引用文の後に、続けて石川氏と剣山城(つるぎやまじょう)黒川氏との合戦の記事も載せており、高峠方に「石川六郎を大将となし」との一文が見える。これは合戦相手が黒川肥前守とあるから享禄年間(2年、1529年か)ごろの出来事で、細川・河野和睦の1381年ごろとは全く時代が異なるのだが、これも『左海予章記』よりの引用文だとすれば、この高峠方の大将石川六郎が、六郎通之と同名であることから、先の細川満之の書状とも重ね合わせて、時代を混同している可能性が考えられよう。この享禄の石川は通説からすれば石川伊予守虎之助か、同族の石川六郎なる人に当たるだろうが、『左海予章記』が通之と取り違えていることも想像される。 これに対して白石友治氏は『伊予史談』63号から66号で、河野通之が石川を名乗るなど論外だと否定しておられる。文書にある石川入道は通之ではなく、高峠城の家老のことだと云う。もちろん二代目の石川信濃守通信も家老で、家老職の石川が代々続いたのだとする。ただし、通之が高外木の城主に納まったとする点においては、『保國寺縁起』と同様である。そして通之の子孫が代々高外木城を居城としたが、河野通存の子通能(兼伊予守)の子息宗三郎の代に至り夭折して絶えたため、その機を窺って家老の石川通清(みちきよ)が城主として新居郡の旗頭に成り上がったのであろうとしている。 たしかに系図によっては河野通存の子に通能の名が認められなくはないのである。しかし、伊予守や宗三郎については、一般に左京大夫通宣(みちのぶ)の別名だとされている。また、通之は通能(通義)の病没後に一時期河野宗家を相続し、通之やその子通元は和気郡の御木寺(みきじ)山城に、通春は湊山(みなとやま)城に、通存や晴通は温泉郡の奥之城に居住したことなどが県内史料に散見されている。それに対して、彼らが新居郡の高峠城に居住したことを示す史料等は上記以外にはほとんど見当たらないのである。 朝倉慶景氏は『石川氏及び天正期東予・西讃の諸将についての研究』の中で、これについては真っ向から否定しておられる。仇敵である細川氏の高峠城に河野通之が居住するなどあり得ないとの論旨である。満之書状の石川入道については白石氏同様、通之説を否定しているが、白石氏が家老石川氏を地元あたりの有力者と見ているのに対して、朝倉氏は広範な史料考証により、この石川氏は讃岐から新居郡に入った細川氏の被官で、高峠城で細川の代官を勤めた石川氏だとしている。 満之書状の年(1389年)には細川頼之が室町幕府の要職に戻ったため、末弟の満之が新居郡を管掌していたが、1392年以後には満之も備中守護代から守護職になり、同時に讃岐や、新居郡も分国支配した。この支配は頼重 - 氏久 - 勝久 - 政春 と満之以後の子孫に引き継がれ、その武威を背景に代官石川氏が代々高峠城で新居郡内を統治したものであろう。これら讃岐からの石川氏の一族が備中においても細川氏の代官を務めることになった。従って伊予と讃岐と備中の石川氏は、古くから細川氏に仕えた同族であり、そのため、後に備中からも石川氏が高峠に入ったのだとしている。ただし、その時期については『澄水記』ほかの大永2年ではなく天文年間あたりかとし、備中石川氏も幸山城主(高山城主)の子ではなく、一族ではあっても、当初に吉備津神社社務代であった別流(頼親流)ではないかとしているようだ。 しかし、姓氏家紋辞典に見える伊予・讃岐・備中に共通する石川氏の家紋は丸に笹竜胆紋(ささりんどうもん)であり、河内石川氏の義家流であって、頼親流の飛び鶴紋ではなさそうである。実際にどちらであるかは、高峠城主石川備中守家の家紋を調べてみれば分かるのではないだろうか。 通之は高峠城主ではないのか
それでは、ほんとうに通之は高峠城には一度も居住しなかったのであろうか。 南北朝の頃、細川氏が新居・宇摩の二郡に進入したため、伊豫国守護河野通直(通堯)は領地の奪還を目指し、高峠城に陣を敷いて細川軍と戦ったが、その10年後、手勢の不備を突かれ、吉岡の佐々久原に自決した。そのため新居・宇摩二郡は再び細川氏の手中に落ちた。高峠城も細川頼之の城となり、この頃に、讃岐にいた被官の石川氏を新居郡の代官として任命したものと思われる。しかし、1381年将軍足利義満は河野の依頼により両者の仲裁をして、河野に伊豫の守護職を安堵し、細川に河野との和睦を命じた。そして、河野通直の嫡男亀王丸を伊豫(東・中予)の守護職に任じ、通義の名を与える。一方で、御内儀の計らいで弟の鬼王丸を細川頼之の養子とし、通之の名を与えることに決まったことが『予章記』に書かれている。長福寺本によると、次のように記されている。 新居郡宇麻郡は大半細川家の衆也。和談之上者不及是非、且一恩にかけて契約の辻にとて細川家へ被遣。この細川家の場所が高峠城とは明言されていないが、この一文には、大半細川家の衆の中でうまくいくのかと心配する気持ちが表れている。この箇所などを読むと、長福寺本『予章記』の著者は「通之は当初は二郡に入ったものと考えていた」としか理解できないようである。足利将軍家のほうでも、河野家の子息が細川家の養子として高峠城に入ることで、両者の間がうまく収拾できると考慮されたからこそ、このように取り計らったのではないだろうか。したがって、二郡が細川氏の所領であっても細川頼之が当地に留まることなどないため、代わりに養子の通之が高峠城主の座に納まったと考えることは、それほど無理な解釈だとは思えない。 むろん、当郡守護の面においては、代官石川氏を通して細川氏が実権を掌握していたことはいうまでもない。細川氏の代官がおらず、通之だけなら、河野家の本領と何も変わらないのである。先述のように、保國寺書状の1389年は細川頼之の末弟満之が新居郡守護に任じられていた年である。その後細川満之は備中守護職となり、さらに後裔が数代続くが、その時期の備中における細川氏の代官が、庄氏と備中石川氏であった。通之(鬼王丸)にとって細川は仇敵であり、細川頼之のほうにも不満があったかも知れないが、この計らいは将軍家の命による約定であり、和睦の条件として個人的な感情の埒外にあった。通之が仇敵の領地に住むはずがないとの考えも成立する一方で、細川の養子となった通之が河野本領に住むのが適当なのかどうかについては、やはり疑念が残るのである。 通之の立場と宗家・豫州家 おそらく通之はそれ以後、河野と細川の両家に片足ずつを乗せる立場に置かれていたのであろう。応永元年(1394年)11月16日河野通能(通義)が25歳そこそこで病没したとき、将軍家は六郎通之を河野家へ呼び戻して河野の家督を継がせた。通能の子が成長するまでの期間という約束でもあった。その通りに応永16年(1409)河野通之は兄の遺志に従って兄の子の河野通久に家督を譲る。この間、高峠城主は不在であったとしても、細川氏の強権をバックとして代官石川氏が差配している限り、特に問題などは起こりえなかったであろう。通之にしてもこうした力関係のバランスは壊したくなかったはずで、河野本家の当主としては本領に石川氏など(つまり細川氏)を立ち入らせたくない思いがあって、壬生川に先鋒の防衛拠点、鷺森城(さぎもりじょう)を築かせたことも考えられる。 しかし、兄通能(通義)との約束とはいえ、通之が河野通久に家督をすんなり譲ったところから、通之の子息や家臣らの間には不満が芽生え、次第に宗家(そうけ)と豫州家の争いというものに発展していったのだろう。豫州家(よしゅうけ)という呼称にしても、通之の子の通元の時代あたりに発祥したのではないかともされている。ただし、この場合の豫州家とは、伊豫国における通之の子孫を指しているのであり、必ずしも高峠城主を指していっているものではないだろう。子孫の中には松山近辺に小城を持ち、新居郡には居住しなかった者も多かったと思われる。新居郡と和気郡は古来有縁なので、あるいは和気郡周辺にでも住んだのだろうか。 もちろん、中には二郡に住した者もいたのかもしれないが、二郡の史料などは焼けて一切残存しないから、この間だれが高峠城主だったのかについては知る由もないのである。ただ、新居・宇摩の二郡が細川の知行であったとしても、河野家のほうでも高峠城との関わりは元より深いものがあり、伊豫一国(中・東予)の守護職が将軍家より河野氏に安堵されていたからこそ、二郡の領主・地頭らも『河野分限録』などに河野一門として書かれているのではあるまいか。細川領・石川領としてまったく河野家に無関係なら、そもそも二郡が河野一門とされるはずがないし、石川氏が河野系図に連なることなどあり得ない話であろう。それとも、1572年の三好勢撤退後は、石川氏も一時期おとなしく河野宗家の旗下に従っていただろうから、この時代の状況を述べたものであろうか。だとしても、それは10年にも満たない短期間と思われる。ほどなく二郡は河野に背を向けて、土佐の長曽我部の軍門に降ってしまったからである。 高峠城と備中石川氏の関係 ともあれ、宗家・豫州家の対立期ともなると、河野宗家のほうでも内紛や、応仁の乱等による混乱が絶えず、また周辺に台頭してくる戦国大名の外圧によって、再び存亡の岐路に立たされ始め、新居・宇摩どころの騒ぎではなくなってきたことが推察される。細川や河野の勢力・威光も次第に衰え、地頭や給人らが勝手な振る舞いをしだしたために世情が乱れ、在地の代官石川氏の力だけではどうにも統率不能な状況に陥ってきたことが想像されるのである。
そのため『澄水記』に書かれたように、当時、備中で主家細川政春を破り備中大半を切り取って勢威を増大させていた幸山城主(高山城主)石川左衛門尉の子息を、河野家と二郡の地頭らが相談して旗頭に迎えようと画策したのではないだろうか。同族の石川氏なら、在地の石川氏側も異論がなかったであろうし、豫州石川氏自体にも後継者が途絶えがちだった場合も考えられ、たとえば養子として迎えたケースもあり得よう。『天正陣実記』には「石川家の相続せば我々も力を添て共に相続すべしとて、追々に馳来り、盟を立て血判をす」とも書いている。備中から養子を迎えたので、石川氏が相続できたのではあるまいか。すでに弱体化した備中守護細川家に遠慮は不要であり、河野氏にとっても国内の無用な混乱を防ぐ意味で、好都合だったのではないかと思う。 つまり、これが『澄水記』『天正陣実記』がいう石川左衛門尉(家久?)の子息なる虎之助で、石川伊豫守と称して二郡の旗頭に迎え入れられたのではないかと推察される。ただ、実際上は二郡の城主に担がれたとしても、名目上の城主がまだ河野豫州家末裔にあったとすれば、表向きは高峠城主にはならず、引き続き代官家を兼ねて引き継いだのではないかとも思われる。備中守ではなく、まだ石川伊予守を号しているのは、そのためではないかと考えられるのである。 しかし、河野宗家もいよいよ窮して、豫州家から2代続けて後継者(実際は弾正少弼通直の実子であるとの系譜もあるが)を迎えざるを得ない事態に到ったため、名実ともに高峠城主がいなくなった。そのため、石川伊豫守の嫡男通清の代になって備中石川氏が代官から高峠城主に成り上がり、備中守を名乗ったのではないかと想像されよう。河野系譜に載る石川通昌は、石川伊予守ではなく、おそらく、この石川備中守通清のことではないかと考えている。石川通昌が名実ともに河野豫州家のあとを継承し、高峠城主になったから河野系譜に載せられたのではないだろうか。通直・晴通・通宣の時代とは年代的にも重なっており、通昌(つうしょう)、通清(つうしょう)と音も合うのである。 石川伊豫守の場合は、事実かどうか分らないが『保國寺縁起』には通房(みちふさ)、『予陽河野家譜』には通久(みちひさ)と記されている。『澄水記』に、東の館には虎千代(通清)が住み、西の館には伊豫守が住んだと書かれているが、朝倉慶景氏はその綿密な史料考証により、西の館が代官家のものではないかと主張しておられる。これらのことから、伊豫守の代には、備中石川氏は二郡の旗頭であったとしても、名目上はまだ代官家の地位であったということが考えられよう。 高峠における石川氏の系譜 石川伊豫守虎之助の書状は焼失したのかどうか1通も認められていない。文書があるのは、石川虎胤、源太夫、通昌、勝重、彦三、四郎虎武である。また通房・通久などの名前も見当たらない。そこでこの辺はかなり想像が入るが、石川虎胤(とらたね)という人が、あるいは虎之助と同一人物だったのかとも推測してみる。また、通清に兄弟がいるのかどうかは不明だが、一人よりは弟がいたとするほうが可能性が高そうである。それが西の館の代官四郎虎武とか彦三という人ではないかと考える。やはり「虎」が付いているので、代々の豫州代官家後裔よりも備中石川氏の一族とするほうが正鵠とまでいわないが、的には近そうに思われる。もっとも、石川伊予守が豫州代官家の婿養子であれば、両家の血筋ということにはなる。 そこで、とりあえず下記のように考えてみた。
先ず以てお断りしておくが、上記は根拠となる多少の史料はあるものの、想像を交えた私見であり、改名などの多くは推測に過ぎない。また、石川彦三については、名前以外には何も分からない。 石川備中守通清は天正12年10月17日に病没したとされていて、保國寺に墓とされる石塔も残っているが、石川四郎虎武は察するに天正の陣の7月14日に落命したようであり、年代を見ても通清よりは若干、年齢が若い程度で、ほぼ同時代の人かと察せられる。朝倉慶景氏も述べておられるとおり、その子息か孫が、『西條誌』の安知生村の項にある、土佐へ行ったという石川弥四郎という人ではなかったか。得永氏宛に「石弥」の名で書簡を出しているが、得永氏の子孫という百姓幸助の安知生村(あんじゅうむら)は西の館に近い。父親か祖父にあたる名前四郎虎武からしても、土佐へ逃れたという虎竹丸ではないかと考えられる。
他方、城主通清には備中守勝重(刑部)という嫡男がいた(この勝重の書状は残っている)。勝重は長曽我部元親の弟親泰の娘を室に迎えて男子が誕生したが、勝重はその後土佐に人質として入り、土佐で早世したとも言われている。そのため、天正10年には、石川伊予守の娘婿である近藤長門守の子息彦太郎を再度、人質に渡さざるを得なかったことも考えられよう。この勝重と親泰の娘の間に生まれた男子が天正の陣に八歳とかいわれている虎千代丸ではないのだろうか。したがって、石川備中守通清は虎千代丸の親代わりではあるが、実際には祖父であろう。年齢からしても45年ぐらい離れている。 子息のその後 天正の陣の際に土佐へ逃れた子息にしても、虎千代丸だとか、虎竹丸だとか、いろいろと伝承が混乱している(別本『澄水記』巻末にもこの点の疑問が呈せられている)。これはたぶん、東の館と西の館の子を混同しているのである。天正の陣の前年に通清が逝去したのち、後見は近藤長門守といっても、代官家の四郎虎武が7月14日までは虎千代丸の親代わりになっていたのではないだろうか。一方で四郎虎武には実子か、孫にあたる虎竹丸もいた。虎竹丸は土佐へ逃れた後に弥四郎その後伝兵衛を名乗ったが、おそらく、親の四郎虎武の名を引き継いだものと思われる。弥四郎の四郎からもそのことが窺えよう。そのため後年様々な混乱が生じたのである。他方、城主である備中守通清の幼名は虎千代だから、その孫の名も虎千代丸の方がふさわしいと思われるので、確証こそないが、当時、虎千代丸・虎竹丸二人とも土佐へ逃れたのではないだろうか。虎千代丸は落城当時8歳と伝えられるが、代官家の虎竹丸は4年後の手紙に長曽我部から与えられた弥四郎の名を書いているので、朝倉慶景氏のいわれるように、そのころまでには元服したと考えられ、たとえば15才だとすると、高峠城落城当時は11才ぐらいではなかったかと推測される。 『西條誌』によると、虎竹丸(石川弥四郎、のちに伝兵衛)は、天正の陣の4年後に得永氏に手紙を書き送った(西条の地名が書き並べられたという文書も、おそらく弥四郎の手によるものだろう)。朝倉氏によると、石川伝兵衛は各地を経巡ったのち1646年に土佐山内家にも仕官しており、1648年まで生きたとのことである。 一方、虎千代丸はのちに治左衛門尉と名乗り、廃城となった高峠城や旧知の子孫の消息を求めて郷里西条を訪れ、保國寺に泊まって、西条在住の久門政武(通清の東の館跡である土居構え屋敷に住んだ人)と当時を嘆じ合ったとの記録がある。 これらのことから推察しても、石川氏には主家虎千代丸と代官家虎竹丸との二人の少年が存在したのではないかと考えられるであろう。残存する史料にも通景(前名虎千代)、通利(前名虎武)と、二人の異なった名前が認められているのであり、通景・通利の「通」は、石川家にも河野家にも共通する名前である。天正の陣後、高峠城は虚しくも廃城となったが、石川氏の嫡流は土佐へ逃れて生き延びたのである。
2010.07.31
『姓氏家系大辞典』(太田亮編著)には、矢野系図に云うとして、以下の系図もある。(越智)玉守……益興……益連……實連……實遠(橘)……實幸……實保……貞保……遠保ここでは、上仙菩薩(千寿丸)は(越智)益連の第二子となっているので、この系図に従うと、越智氏=矢野氏となり、玉守が一宮神社社家を兼ねていたということになる。そのため橘実遠と矢野実遠が同一人物とすれば、年代的には上仙菩薩のほうが橘実遠よりも前なので、この系図の順序は適合している。したがって、上仙菩薩は矢野実遠の子ではなく、矢野益連の子が正しいのかもしれない。 ◆ 関連ページ 22.石川・黒川合戦年考 ■ 参考文献等
『姓氏家系大辞典』太田亮 保國寺文書 『萬年山保國禅寺歴代略記』 『小松邑志』 伊予史談会双書 「高峠の河野氏と石川氏」 白石友治(『伊予史談』63~66号) 『石川氏及び天正期東予・西讃の諸将についての研究』 朝倉慶景著 『伊予の古城跡』 伊予史談会双書 『澄水記』 『天正陣実記』 『西條誌』 『予陽河野家譜』 『愛媛県史』 『西条市誌編纂餘録』久門範政著 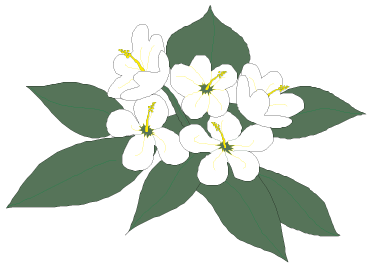 RELAX TIME RELAX TIME
|







