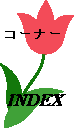NO.2 東宝・芸術座の「放浪記」が昨年12月に1500回の上演数を記録し、主演女優の森光子さんが先頃、第7回読売演劇大賞を受賞されました。昭和36年初演から38年かかって達成されたそうです。 それに関連して、もう20数年前にもなるのですが「放浪記」と題して書いた拙文を思い出しました。 小文ながら今回はそれを掲載し、林芙美子を偲んでみました。 平成12年2月
「放 浪 記」 私の部屋に林芙美子の詩を書いた額がぶら下がっている。知人が新婚旅行の土産に買ってきてくれたものだ。椿の実と松のボックリで梅の花枝に仕上げられた細工絵の傍らに″花の命はみじかくて苦しきことのみ多かりき″の詩句が書かれ、下に小さく「別府」の文字が入っている。「なぜ別府と関係があるのだろう……」などと思いながら、私は寝転んでときどきそれを眺めている。 |