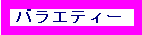
NO.11
芙美子の「帰郷」
私は宿命的な放浪者である。私は古里を持たない。父は四国の伊予の人間で、太物の行商人であった。母は九州の桜島の温泉宿の娘である。母は他国者と一緒になったというので、鹿児島を追放されて父と落ち着き場所を求めたところは、山口県の下関というところであった。私が生まれたのはその下関の町である。
芙美子は『放浪記』の冒頭でこのように書いているが、彼女が生まれたのは下関ではなく、門司であった。その当時は、自分の誕生時の状況など細かく知っている人は少なかったかもしれないので、「下関」とあるのも、文学上のフィクションというよりも、芙美子自身がはっきりと覚えていなかったせいではないだろうか。
門司生まれの芙美子の母親はキクさんといった。キクさんの元の旦那は、文中にある伊予の太物の行商人で、その名を宮田麻太郎という。つまり、芙美子の実父であるが、その麻太郎の実家がほかでもない伊予の周桑郡(しゅうそうぐん)吉岡村新町(現在の西条市新町)にあって、当時「扇屋」という雑貨商を営んでいたのである。
芙美子の両親は、芙美子が生まれた門司から、下関・若松へ移動し、その若松で事情があって離縁している。母キクと同伴したのは父の雇い人で母より年下の養父「沢井喜三郎」だった。そのため、8歳の芙美子も二人とともに行商の旅に出ざるを得なくなる。それでもようやく落ち着いた尾道の町で、小学校を卒業。尾道市立女学校に通って読書に励んだり、文学の道にいそしみながら暮らしていたのである。
その市立女学校4年生の一学期に、芙美子は初めて実父麻太郎の郷里、周桑郡吉岡村新町を訪れたようである。実家の祖父が亡くなったための、母キクの代理であったと思われるが、その地を芙美子は「ニユ川」と書いている。「ニユ川」は実際は実家のある新町の近くの町で、彼女が船を下りたところであった。
そのニユ川(壬生川)の駅前に、22歳の暮れに芙美子が東京から麻太郎に書き送った手紙の一文が、現在、記念碑になって残されている。
何もかも忘れ
この不幸な私を
父上は
愛して下さるでせう
芙美子
父上様
また、実家近くの佐志久山(さしくやま)にも、芙美子の「帰郷」という詩が、道端の碑石に刻まれている。
帰 郷
ふるさとの山や海を眺めて泣く私です
久々で訪れたふるさとの家
昔々子供の飯事に
私のオムコサンになった子供は
小さな村いっぱいにツチの音をたてて
大きな風呂桶にタガを入れている
もう大木のような若者だ
小指をつないだかのひとは
誰も知らない国へ行っているってことだが
小高い密柑山の上から海を眺め
オーイと呼んでみようか
村の人が村のお友達が
みんなオーイと集まって来るでしょう
芙美子が壬生川の地を訪れたとき着想して詠んだ詩と伝えられるが、芙美子は幼少時から北九州・下関を中心に各地を転々としていて、父の実家を訪れたのは、おそらくこのとき一度きりであった。子供時代に伊予の新町で遊んだ体験などは皆無であったと思われる。つまり、父の実家のある新町は、彼女にとって現実的にはこの詩に詠っているような「ふるさと」でも何でもなかったはずである。たとえ佐志久山から眺めた風光を素材に「帰郷」の詩を詠んだのだとしても、この詩の主題は、どこの土地ともいえない「想像上のふるさと」を書いているとしか思われない。
にもかかわらず、あえてこのような詩を書いているのだとしたら、「古里を持たない」という林芙美子の内奥にも、無籍のまま離別された麻太郎に対する反発とは裏腹の、実父への熱い思慕の念と、実家のふるさと「ニユ川」へのほのかな憧憬のようなものが、一つの原風景となってどこかに息づいていたのかもしれない。
平成23年03月25日
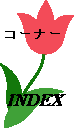
|
|