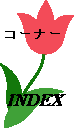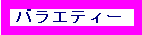
NO.6
〜『戦争と平和』雑感 〜
ぬけるような秋空を見ると、きまってロシアの深い空を思い出す。白樺林や広大な原野の上を白雲が上昇したり下降したりしながら流れ過ぎてゆく高く青い空 ――それは、そのままトルストイの領地ヤースナヤ・パリヤーナの森に拡がる乳色の空であり、戦地アウステルリッツへとわれわれをかりたててゆく『戦争と平和』の、あの空である。
『戦争と平和』の場面で、私がまず思い浮かべるのはアウステルリッツの戦場であおむけに倒れているアンドレイ公爵の姿である。
ペテルブルク社交界での虚偽に満ちた人為的な生活にあいそをつかした青年公爵アンドレイ・ボルコンスキイは、ロシアの総司令官クツゾフ将軍の副官となって戦地におもむき、軍旗を拾って走るうちになぐられて負傷した。そして、すべてから遠ざかった世界で無窮の空を見上げる。その体験を通じて、彼は瞬間にしてすべてのことを理解した。生きている誰もが理解しえず、説明することもできなかった生と死の虚しさというものを、彼は知ったのである。
いったん彼のうちにめばえた死の空虚は、彼の人生を一変せしめた。彼は、ナポレオンへの尊敬も、おのれのツウロンも捨てて自分の領地に蟄居してしまう。彼の生への喜びも今は死を通してしか感じることはできず、ナターシャの愛も、いちどは彼女によって生をよみがえらせながら、その芽を摘み取られていったアンドレイの心を、死の世界から、ついに取り戻すことはできなかった。彼はボロジノ会戦の傷がもとで死んでしまうのである。
しかし、アンドレイ公爵の死は、その妹マリアと、婚約者ナターシャとの親交を可能にした。孤独な信仰に生きる敬虔な乙女マリア、若さと生そのもののように明るく能動的な娘ナターシャ――この昼夜のように相反する信仰と自然の世界は、互いに反発し合い、二人は相手に好意を持てずにいたが、アンドレイの看護を通して形而上学的な死の世界に触れた今は、互いを理解できないままにも受け入れてゆこうという気持になったのである。
また、モスクワから敗走するフランス軍を追って騎兵隊長ジェニーソフのもとを訪れたペーチャ・ロストフが、奇襲前の明け方の野営地の自然をうつらうつらのうちに眺める幻想的な場面もたいそう美しく、印象に残る。その朝、祖国ロシアと皇帝への崇敬の熱情から、若い命を白玉と散らしたペーチャ。その攻撃でペーチャは頭を撃たれて死ぬのである。だが、その突撃はピエールを含むロシアの捕虜たちを、フランス軍と死から解放したのであった。
ピエール・ベズーホフはこの作品中、最も中心的な人物で、アンドレイとともに作者の分身の位置を与えられているという。モスクワの富豪ベズーホフ家の私生児として生まれたピエールは、外見的には怪力ののろまな巨漢にすぎないが、フランスで学んだ進歩的な思想の影響を受けて、つねに何かを考え、悩んでいる。無謀な行動を平気でとるかと思えば、子供のように純真である。
しかしピエールは、彼の財産を目当てにしたワシィーリイ侯爵の術策と、妖艶なその娘エレンの色香に迷ってエレンを妻とし、その妻の不貞から決闘の相手ドーロホフを傷つけてしまった。自分の内奥の罪の恐ろしさに苦しみ、自己嫌悪した彼は、いっさいを捨ててマソンという秘密結社に入ってしまう。マソンでの仕事、やがてフランス軍のロシア侵入、ボロジノ会戦、モスクワ放棄…と激動する環境の中で、彼の生活に欠けていたロシアの国民精神に触れて彼の苦悩もいやされるかに見えたが、モスクワでのロシア人捕虜の銃殺場面は、彼を再び絶望の谷底へと突き落とした。しかし、けっきょくは、プラトン・カラターエフとの捕虜生活によって彼は再びいやされ、ロシアの勝利を記念するかのようにナターシャとの幸福な生活に入ってゆくのである。
ピエールと同様に、マリアと結婚して幸福な家庭を持った熱血漢ニコライ・ロストフは、若いときからロストフ家の没落の重荷を両肩に背負ってきた。母親は公爵令嬢マリアとの結婚を心から喜んだ。というのも左前になったロストフ家を救うてだてはこれしかなかったからである。しかし、勇猛果敢な青年将校時代のニコライは軍隊においても、モスクワにおいても、周囲の敬愛を一身に受けて充実した日々を送っていた。この実戦型の闊達自在で勇ましい青年は、剛胆明朗なドーロホフとともに『戦争と平和』の中でもわれわれの愛情を勝ちえやすい存在であろう。
このニコライを愛するもう一人の娘、いとこのソーニャは幼少からロストフ家で養育されていたが、両親の反対ともちまえの犠牲的精神を愛する性質からニコライとは結ばれず、幸福の影に甘んじる女性に描かれている。
『戦争と平和』は多くの登場人物を擁して、ロシアと、自然と、戦争と、貴族社会と、その中で生長する彼らの運命と事件をパターンとして、網の目のように発展させてゆく。トルストイの構成と描写は驚くほどちみつだ。
シェングラーベン、アウステルリッツ、ボロジノと会戦のたびごとに全く異なる戦闘場面は、作品の完成にいかに五年を費やしたとはいえ、会戦の場に居合わせた小才ごときとても及ぶものではあるまい。このような戦闘描写は『イーリアス』にも匹敵するものではないだろうか? また、その自然描写の雄大さ、美しさには、翻訳に負うところもあろうが、感嘆せざるをえない。トルストイの自然描写は定評があり、オトラードノエでのロストフ家の生活、アンドレイ公爵の領地の森の描写などは、単に美しいばかりでなく、実に生き生きと情感がこめられている。或いはまた、華やかな舞踏会の場面なども、詳細な描写で、あざやかに浮かんでくる。
『戦争と平和』を動かすトルストイの歴史観は、運命論的な歴史観であるといわれる。したがって、彼はナポレオン的な英雄というものを承認せず、それは巨大な潮流の先端に立つ一つの波頭のようなものにすぎないという。その意味で、たしかにトルストイは戦争や自然の前で人間――それが主人公であっても――を卑小に描き切ったが、彼は決して人間をこのようにだけ描いたのではなく、その世界の中でそこを突き抜けてゆく人類を代表する個人の魂の強い生の姿勢が、カラターエフを知ったピエールなどには見られるのである。このように自然や運命と結びついてこれを克服してゆく道徳的な英雄を、トルストイは認めている。彼のいう「忍耐」も「時」も、つまりは自然や運命に誠実な生き方の一表現にほかならない。彼は虚偽に満ちた人為的な生活をこの世界の一面の真理とは認めながらも、このような生き方を否定し、きらった。
こうしたトルストイの作品は、人間主義を標榜する者、社会の底辺や人間の心の暗部を通して愛をたしかめようとする読者からは、あまり興味を持たれず敬遠されることもある。しかし、自然や人生に向けられたトルストイの愛がいかに強いからといって、それで人間への愛が希薄になるわけでなく、トルストイの愛もドストエフスキイの愛も、根本は一つである。われわれがどちらか一方を否定するとき、その愛が不完全なものになることは必定だろう。
『戦争と平和』の主人公たちは決してわれわれに遠い存在ではない。現代のように、自然と愛と理想から離れ、自己中心的な日々の生活に追われている時代には、むしろ、彼らは周囲の人々よりも身近な隣人であるかもしれない。われわれは彼らと親しむことによって、彼らの世界へ踏み込もうと、逆に何かを引き出そうと、また互いを結びつけるものに向かって努力してゆこうと、それは人それぞれの勝手である。『戦争と平和』は、その要求に十分こたえてくれるだろう。
ともあれ、私はまた生活へと帰ってゆかなければならない。ナターシャ、アンドレイ、ニコライ、ピエール、ペーチャ、マリア、ソーニャ――ごきげんよう。ジェニーソフ、ドーロホフ、トゥーシン、ボルコンスキイ、ロストフ一家、ドルベツカーヤ、プラトン・カラターエフ――また会う日まで。そして、晩年は不幸であったと伝えられるトルストイ翁――そして、広大な原野と白樺林。そして、私のロシアの空よ――あの絶対的な力をもって人間をその運命のうちにやさしくつつみ込むように生と死を反映する無限の空間よ――ひとまず、さらば。
(昭和45年記)
|
2000年12月.
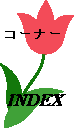
|